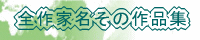芸術論(岡村孝子論)
=改編版=
真善美
* * * *
宇宙の本質は静寂や穏やかさであり、
その現われはひたむきさや悲哀である。
ときとして天空を支配する最高神(天帝)は、
愛娘をこの地上に舞いおらせることがある。
そのあまりの出来のよさを地上の人間たち
に見せびらかしたいがためである。
芸術は人間の精神活動によって生まれるが、
その本源は不合理性や反自然性や非現実性
にある。
* * * *
私たち生き物は、宇宙生成以来、その物質性として、
重力や電気や電磁波、そして空気振動である音などの物
理性と密接に関わりあいながらここまで進化してきた。
だから私たちはその物質性や物理性のもつ合理性や自
然性や現実性にいやおうなく支配されがんじがらめにさ
れている。
この世に生まれて死ぬまで私たちは誰ひとりとしてそ
の苛烈な制約から逃れることはできない。
だがそのような生き物が人間となるまでの進化の過程
で、精神と云うものを芽生えさせ発達させて、それが肉
体とはまったく別物であるかのようなものとして獲得し
てきた。
そして精神は、本来肉体(自然的合理的現実的なもの)
もとで成り立ち、ほとんどその制約下にあるにもかかわ
らず、自分は肉体から独立してだけではなく、あたかも
自分がが肉体を支配しているかのように勘違いをするよ
うになってきた。
だがそれは虚妄である。
そのことによって私たちはどんなに痛い目に合わされ
てきたことか。
精神はその進化の過程で何度も自然の物質性に押しつ
ぶされ叩きのめされてきたに違いない。だがやがて、知
性と想像力が達していくにしたがって、人間は自然を支
配し利用するようになり、人間の精神は肉体からは独立
していて自由であること、そして自由な精神を持つこと
が人間の本質であり価値であることを信じるようになっ
て行った。そのことに大いに寄与したのが人間の想像す
る力の確立とその発達であった。
その後想像力は知性と協力しながら世界各地に文明を
興しさまざまな文化を発展させていくことになる。
さて精神が自由を獲得していることに自信を持ったと
しても、思い通りには行かない現実の生活や、肉体の死
によって起こる精神の消滅の恐怖からは逃れることはで
きなかった。
そのままでは人間は苦悩と恐怖に打ちひしがれ、もは
や精神には絶望しか残らないはずであった。
もし私たちの先祖たちが、そのとき自分たちは自由な
精神を持った人間であることを放棄してしまったら人間
は再び動物のように生きていかなければならなくなった
に違いないのだが、でも先祖たちは、その自由な精神活
動の結果としての様ざまな芸術活動や宗教活動に力を借
りることによって、その精神の崩壊の危機を乗り越える
ことが出来たに違いなかった。
このように精神は無意識のうちに自然や肉体の支配や
制約を受けていることに不満や苛立ちを感じながらも、
次第に進化を遂げていく知性や想像力によって宗教や芸
術を生み出すようになていった。
そして芸術や宗教は精神の不満や苛立ちを和らげるだ
けではなく、それによって人間は慰藉され洪水のように
押し寄せる苦痛や不安から開放されようになると、精神
は自分があたかも自然の物質性や周囲の物理的世界から
自由になっているかのように感じるようになっていった。
では具体的には
不合理性や反自然性や非現実性としての芸術とは
どういうことなのだろうか?
[詩の場合]
このような詩がある。
—-赤い鳥小鳥
なぜなぜ赤い
赤い実を食べた—-
(北原白秋)
この詩を意味としてみた場合は次のようになる。
目の前に赤い羽根をした小さな鳥が
存在しています。
なぜ羽根が赤いんだろうと疑問を持ちます。
推測するにたぶん赤い実を
食べたからでしょうか
そしてこれを合理的な表現とすれば次のようになる。
目の前に赤い羽根をした小さな
鳥が居ます。
なぜ赤い色をしているのかとても不思議です
おそらく赤い実ばかりを食べている
からでしょうか
だが作者が赤い小鳥を見て伝えたかったのは
このような意味であろうか?
それは違う、それでは詩にはならない。
作者が詩として伝えたかったのは赤い小鳥を
見たときの詩興である。
それは次のようなものだったに違いない。
詩人は日常の雑事に煩わされることなく
心の平穏を保ちながら開放的に生活して
いる。そんなとき籠に入った赤い羽根の
小鳥を目にする。
詩人の曇りない目にはそのいたいけで
可憐な生き物は新鮮に映る。
小鳥は人間からみれば取るに
足らない存在であるが、
詩人は人間と同じように知恵を持っている
生き物であることに気づく、
そして人間とはまったく違う外見、
しかも鮮やかなほどに赤い体色をしている
にもかかわらず人間と同じように自分とい
うものを持って生きていることに共感しな
がら、その存在の不可思議さに驚き感嘆
する。そしてこのような小さな生き物だけ
ではなく人間を含めたすべての生きとしい
けるものが、何か人知では推し量ることが
出来ないような天の理法や造物主の意思の
もとで生かされているに違いないというこ
とを驚嘆と共に天啓のように受け取る。
そしてこのような興奮や感動を表現するには以下
のようなものにならざるを得ないのである。
「赤い鳥小鳥」
意味としては、反自然的で不合理な
繰り返しであるが、
それによってただならぬもの何か
尋常でないものを
指し示そうとしていることが判る。
今目の前にいる赤い小鳥は日常
普通に目にしている
単なる赤い小鳥ではないということを
強調しようとしている。
「なぜなぜ赤い」
この”なぜなぜ”の繰り返しは
自然的合理的な解答をを排除
していることであり、
そのことによって今沸き起こっている
昂ぶる詩情を詩として
成立しうると感じている詩人の直感
によるものである。
「赤い実を食べた」
”なぜ赤い”という問いには、
字義的にはその答えは環境的にとか
遺伝的にとかという
科学的なものになるはずのものなのだが、
詩であろうとする限りそうはならない、
それでは味も素っ気もない、
今感じている驚きや感動を詩として
伝えるには、
誰もが考えるような自然的合理的な
答えではなく、
まったく思いもよらないような答えがが
ふさわしいのである。
それが真実である必要はないのである。
つまり”赤い実を食べた”から赤くなったのだ
という妄想と思えるほどに児戯的で
しかも非科学的なことを信じたいくらいに、
もうありきたりで自然的な表現では
納得できないくらいに
詩人の驚きや感動は深遠で
あったということなのである。
そしてこのような芸術的な表現は
何万を語を費やすよりも
はるかに読者の心に訴え、常日頃合理的
なものにがんじがらめにされ
頑なになっている私たちの心を解きほぐし
豊かにするものなのである。
* * * *
[音楽の場合]
音とは、
空気の振動を耳の鼓膜で受け止め、
それを電気信号にかえて脳に送り、
そこでその振動の強さ弱さや
高さ低さを認識することである。
と言ってしまえばそれまでであるが、
これはあくまでも科学的な見解で、
ほんとうに退屈でつまらない。
それに音がどのように精神(心や意識)に働き
かけるかを知るにはこれでは不十分である。
視覚の働きは可視光線の媒介によって
遠くのものまではっきりと認識することが出来る。
でもある意味限定されているといってもいいだろう。
それはほとんどが前方だけで、しかも暗闇では機能
しないからである。
それは感知する空間が限られていることを意味し
ている。
そしてそれは目に見えている限られた空間だけが
現実的な意義を持っていることを意味している。
では音の場合と云うと、
それは前後左右暗闇に関係なく全方位的に音と云う
も のを認識できる。
それは自分を取り囲む全空間で起こっていること
が自分と関わりあっていることであり、精神にとっ
てはそのことは視覚とは比べ物にならないくらいに
重要な意義を持っていることを示している。
たとえば大勢人がいるところで誰かが声を発すれ
ば、それは自分だけではなく、他のすべての人にも
聞こえているはずである。
それはつまりは周りの大勢の人たちと、その声を
共有していることを意味している。そしてその音に
よって自分と周りの大勢の人たちがいっしょに同じ
ことを感じ同じ気持ちになっている、いわば共感し
ていることでもあり、そのことは意識の共同性にも
つながっているのである。
もし誰かが喜びの声を上げればその感情は周りに
伝わり、その場の雰囲気は喜びに満ちたものになる
だろう、もし逆に悲しい声を上げれば周りの者たち
は不安になリ、その場は沈んだものになるだろう。
その点視覚の場合は何かを目にしているものだけし
か判らないので、その出来事の意味の伝播性は遥か
に低いのである。そのため視覚が意識の共同性や共
感性に果たす役割は聴覚よりも遥かに低く、それほ
ど重要性を持たないのである。
聴覚の全方位性とは、意識を取り囲む物質的な
全世界との関わりを意味しているので、精神活動に
おいてはかなり重要な意義を持っているといえる。
その意義とは共同性や共感性であるが、それは視
覚などよりも遥かに強く精神に組み込まれていて自
動的かつ無意識的に起こるものであり、私たちの精
神の本質といってもよく、言い換えれば人間の共同
性は生まれつき備わっているといってもいいくらい
である。音は視覚のように単純に物の存在を知らせ
るだけではなく、むしろ人間の感情を知らせ伝播さ
せることで重要な役割を果たしてきたようだ。
たとえばサルの群れのように、危険を知らせる声
を発すれば、その声は群れ全体伝わり、群れ全体で
警戒するようになる。そして意味なく興奮したサル
が奇声を上げれば、その声は群れ全体を不安にして
興奮したものなりだろう。
だが人間の場合、音は危険や興奮の知らせる物理
現象というよりは、むしろそれを楽しむ芸術として
進化を遂げて行ったようだ。
音階は周波数の違いである。
ハーモニーはその音階の組み合わせである。
そこには法則性があり合理性があり科学的に解析
できる。
だが自然には音階はなくハーモニーもない。
人間だけがそこに価値を意味を見い出し楽しんで
いる。
どのような音の組み合わせがメジャーとなりマイ
ナーとなるか、科学的には解析できる。
だがなぜ、それに楽しさや悲しさを感じるかは、
科学では判らない、私たち人間がそう感じるから
そうなんだとしか言いようがない。
音楽は時代とともに進化発展してきた。
現代ではリズムが特に重要視されるようになって
来ている。
それにはアフリカ系の人たちの関与が大きかった
ようだが、かといって、大地で踊るアフリカ人た
ちのダンスを見て、その独特のリズム感のよさか
ら、リズムは自然なものだと考えてはいけない。
自然には音楽に見られるようなリズムはない。
彼らのリズムは高度な精神活動の結果なのである。
そしてそれがどれほど彼らに喜びや勇気や夢を与
えていることか。
もしわたしたちの世界が合理的な解釈ができる
だけものだったら人類はとうの昔にその物理的外
界に押しつぶされ死滅していただろう。
未発達な知性や想像力は返って人間を不安にさ
せ憔悴させたに違いなく、もう動物に戻ることの
出来ない人間にとっては絶望しかないからである。
私たちにとって、音楽を聴くとは、そこに表現
されている様ざまな感情や思いや感覚に、私たち
自身がひきつけられとらわれ、そして心からそれ
らに身をゆだねることである。それはほとんどの
場合は共感であるが、個人的な好みだけからそう
するのではない。それは音が先験的に持っている
共同性によるものである。つまり今聴いている音
楽は自分だけが聞いているのではない、他の多く
の人たちも同時に聞いている、だからいま自分は、
その多くの人たちと同じ気持ちになって何かを
(この場合は主に情感)を共有していると感をじて
いるのである。
これらから音とはその場の空間を占めている誰に
も聞こえているものであり、その場の誰にも同じ
ような情報を与えるとともに、その場の誰にもお
なじような感情を呼び起こすのある。
つまり精神的には音=集団性であり、その内容
によっては、集団を興奮状態にさせる可能性を常
にはらんでいる。
* * * *
そのような音の持つ特性を芸術的に発展させて
きた音楽は、1960年代その発展の速度を急速
に速めていった。
その内容は、それまでなかった新しい感覚のも
のや新しい思想や情感が表現されたものだった。
それを支えたのは主に天才的な作曲家や演奏者で
あったが、メディアの発達と普及によるおかげで
もあった。
ラジオ、テレビ、レコード、テープレコード、
有線放送の普及は全国的なものとなり、音=集団
性は全国規模となり、その共有性や共感性の規模
は日本人の数を無意識のうちに含むものとなった。
だがそれだけではなかった。それらのメディア
によって、外国の映画や音楽がどんどん流される
ことによって、音=集団性、そしてその共有性や
共感性は世界的規模にまで広がった。
当時の音楽はどんなに新しく創造的であっても、
その当時の時代状況にあわせもの、また商業主義
の要請に応えた流行的なものでしかなかった。
そのためか70年代に入ると、その発展と勢いは
その後の絶頂期を目指して猛進を始めた。そして
いつしか、音楽業界は花形産業になっていた。
新旧を問わずどんなジャンルの音楽にも勢いが
あった。
現在では想像も出来ないほどのさまざまなジャ
ンルの音楽が、すべてのメディアを通じて終日あ
ふれるように流されていた。クラシック、ジャズ、
演歌、歌謡曲、青春アイドル歌謡、民謡、ポップ
ス、フォークソング、ニューミュージック、シャ
ンソン、カンツォーネ、ボサノバ、アルゼンチン
タンゴ、コンチネンタルタンゴ、ギターやバァイ
オリンの独奏曲やオーケストラ演奏、そしてイー
ジーリスニングを演奏する多くの楽団などなど。
だがどんなに日々の生活に音楽があふれていて
も私にとっては、それほど重要な関心事ではなく、
あくまでも移り行く時代の背景に過ぎなかった。
だから私は、隆盛を極める当時の音楽に耳にして
いても、その演奏会に出かけるとか、レコードを
買い求めると云うことはまったくなかった。
80年代になった頃、私は次第にそのような音
楽に距離をとるようになったいた。このことは私
個人だけではなく、社会にもそのような雰囲気や
傾向があった。60、70年代に隆盛を極めた音
楽の熱狂や興奮から覚めていくような情況があっ
た。かといって私はまったく興味を失ったという
訳ではなく、”今現在流行っている歌”といことで、
娯楽として楽しみながらテレビを見ていた。
もしかしたら私は当時、心の底から興味を抱い
て、そのような音楽を聴いていたのでなく、社会
を巻き込む音楽の興奮性や集団性に浸っていたの
かもしれない。なぜなら、その集団性とは、社会
への帰属性をも意味しているからである。
当時私は日本(広くは世界)で起こるあらゆるこ
とに批判的な考えを抱きながら生きていた。本来
ならその行き着く先は社会から孤立離反してかな
り生きづらいものになっているか、最悪精神に破
綻をきたしていたかに違いないのだが、実際は分
別をわきまえた普通の構成員として生きていた。
何かが私を常識人に押しとどめていたのだ。その
”何か”とは私にとっては音楽にだったに違いない。
音楽による興奮性や共感性に身も心もゆだねるこ
とによって、いま自分はこの世界(日本)に帰属し
ているということを無意識的に感じながら、その
心の奥底から安心感によって精神の破綻を免れて
いたに違いないのだ。
* * * *
このころまでにどのような曲想(楽器と編曲)
で、どのような歌詞を盛り込めばが流行るかが
すでに確立されていた。
それまで音楽の発展を支えてきた有能な作曲
家や作詞家はその要請に応えることが出来てい
たからである。
そのマンネリズムと商業化が私を流行歌から
遠ざけて行ったおもな理由かもしれない。その
決まりきった歌詞や曲想に飽きが来たと云うこ
とで。しかし流行を引っ張利、流行り続けるこ
とが運命付けられているものなら、そこには必
然的に変化が伴っていた。それまでとは違う何
か新しい曲想(楽器と編曲)やリズムのものへと。
たしかにそのようなものは新しい感覚として魅
了する。評論家の小林秀雄はジャズには観念
(思想)がないといった。でもジャズにはそれ
までにはなかった新しい感覚があり常に隠れ
た思想が示唆されていた。
音楽における新しい感覚は精神を更新させる。
もちろん有能な利害関係者はそれに応えること
が出来ていた。ただ相変わらす歌手の歌唱力は
それほど問題ではなく、相変わらずメディアに
取り上げられる話題性や新奇性が大きな比重を
占めていた。
私が音楽に覚めていくようにメディアもその
取り上げ方に少しずつ変化をして行ったようだ。
なぜなら新しい音楽と云うものは時代とともに
古くなっていくものであるからだ。
それでも勢いが衰えないものもあった。アイ
ドルと演歌であるが、何十年たっても今もって
曲想と歌詞内容はそれほど変っていない。青春
アイドル歌謡と演歌は永遠に不滅なのだろう。
歌謡界はいつの時代も新しい曲想や感覚を提
供できる天才によって繁栄してきているのであ
るから、あのどのような楽曲が流行るかがすで
に確立されていた80年代も、そういう意味で
は新たな才能の出現を待ちわびていた時代なの
かもしれない。
* * * *
* * * *
私が最初に姫女を見たのはテレビのザベストテン
と云う番組だった。
たしかそれまでに、ラジオか何かの情報番組で姫
女たちを《あみん》として知ることができていた。
どこかの音楽祭でグランプリを受賞したデュエット
であると云うこと。
初めてその曲を聞いたとき私は姫女たちが持って
いる感性が、それより少し前の時代の若い女性たち
がもっていたものに近いものを感じた。
少し前の感性を判りやすく言い換えると、戦後の
女性たちの感性、または田舎娘たちの感性と言い換
えてもよい。皮肉っぽく言うと、六十年代までは数
多く生存していたが、それ以降急速に数を減らして
行き、今では絶滅危惧種となってしまった女性たち
の感性のことである。
姫女が《あみん》として初めてそのザベストテン
と云う番組に登場したとき、二人は司会者である久
米ひろしと黒柳徹子に挟まれていた。そのとき黒柳
徹子は聴視者の質問として二人に次のように問いか
けた。
「二人は暗いんですが・・・・・」と。
そのとき私はドキッとした。そしてとっさに思っ
た。なんて事を訊くんだと。私はテレビ局や二人の
司会者の無神経ぶりに怒った。まあ、繊細さのかけ
らもない司会者だからしょうがないのかな、とも思
った。でも私にはその後の記憶がない。姫女たちが
どう答え、どんな表情をしたのかも。
おそらく私はその様子をを聞きたくも見たくもな
かったので、チャンネルを変えるか、トイレにでも
立ったのだろう。
たしかに彼女たちの雰囲気には微妙に違和感あっ
た。というのも当時の時代が要請する女性たちのイ
メージというのは、より積極的に自分を前に押し出
すものへと変化してたからである。さらに当時は奇
才タモリなどによって《ネグラ》と云う言葉が姫女
たちのような性格の人間を揶揄する言葉として言い
広められていたせいもあったのだろう。それに比べ
て彼女たちは本当に控えめで大人しかった。少し怯
えているようにも見えた。だから雰囲気としては絶
滅危惧種的な女性たちとして、視聴者の眼に映らざ
るを得なかったのは仕方がないことだったかもしれ
ない。
そのせいか私にとってそれが姫女をテレビで見る
最後となった。
私はテレビ番組のそう云う扱い、と云うよりも当
時の社会の姫女たちに対するそう云う扱いに対して、
憤慨落胆しながらも、時代の流れなのだから仕方が
ないのだと自分に言い聞かせてはいたが、その反面
《少し時代遅れな乙女心を歌う可愛らしい美少女た
ち》と云う話題性で売れているんだなと思いながら、
いずれはその絶滅危惧種的な性格が理由で、そのう
ちに忘れ去れていしまう存在だろうと、なんとなく
も感じていた。
そのとおりであった。それから数年私は偶然とも
思えるように衝撃的な出会いまで、ほとんど姫女の
ことは忘れていたのである。
* * * *
最初にして最後に姫女をテレビて見て以来、姫女
について何の情報も得られなかった私は、やはり予
想通り時代の要請に応えることが出来るような音楽
家には成れなかったなと思った。
それが絶滅危惧種的な性格によるものか、才能の
無さによるものかは判らなかったが、音楽に対する
私の興味の変化からすれば、それほど関心のあるこ
とではなかった。
その時期は八十年代後半、当時私は四十歳を前に
してなんとか《地獄のような青春》くぐり抜けると
ともに、どうにか社会との折り合いも付き、ようや
く自分も人並みに生きていけそうな自信を獲得しつ
つあった。
そして歌謡界には六七十年代のような闇雲な熱狂
や興奮はなくなり、それとは別の洗練された熱狂と
いうべきようなものに少しずつ変化して行った。
その主流を成していたものが、移り変わる流行の
ファッションや洗練された町並を反映するかのよう
に新しい感覚をかもしだしながら、あたかも時代を
先取りするかのような雰囲気をただよわせていた音
楽であった。それはオシャレでかっこいいものとし
て、主に若い世代から熱狂的に支持されていくよう
になり、永遠に不滅な青春アイドル歌謡や演歌と共
に音楽業界を牽引していた。
それでも私は音楽に対してもほとんど興味はなく
なっていき、途切れることなくメディアから吐き出
される音楽もめまぐるしく変化していく時代の背景
を通り過ぎ去っていく装飾に過ぎなくなっていた。
そして私は偶然のように姫女の楽曲と出会う。
それは穏かな秋の日、私はのんびりと午後の
ワイドショウを見ていた。
そして何となく聞いていたエンディングの歌に
私は心を奪われた。
その歌から私は、どこまでも広がろうとする情
感の細やかさや深さ、そして心情の豊かさが感じ
取られた。
それは衝撃的であり、それまでの歌謡曲からは
全く感じられないものであった。
翌日もエンディングまで待ってその曲を聴いた。
曲名は《夢をあきらめないで》作詞作曲歌は姫女
とわかった。
もと《あみん》のどちらかであることも判った
が、でもそのときはどうでも良かった。
私は生まれて初めてレコード(このときはカセ
ットテープ)を買い求めることを思いついた。
そして私は町のレコード店で姫女のアルバム
《After tone》を買った。
なぜ私はこの歌に魅入られたのだろうか?
それはこの歌からあふれ出る心情の豊かさ、
しかも情感の細やかさや深さに裏付けられたと
ころの真正な《心情の豊かさ》にあるのである
が、それは言い換えれば純粋な《生の肯定》の
表れのように直感したからに違いなかった。
たしかにそのとき私は、それまで長いあいだ
の生きることへの積極的な意味を見いだせなか
った青春時代と違って、ようやく自分も人並み
に生きていけそうな自信を獲得しつつあったと
きであるので、私の内部にも《生に対する肯定
感》が多少とも芽生えていたにちがいなく、
そんな私が、どうみても人生を知り尽くしたと
は思えない若い女がこんなにも自然に、そして
高らかに《生の肯定》歌い上げていることに驚
くとともに、心の底から共感したのであろう。
ここではっきりと言っておかなければならな
いことは、この歌に《生の肯定》が表現されて
いるといっても、姫女が《生の肯定》を言葉と
して、たとえは教訓のように”生きていること
は素晴らしい”とかというように、直接表現し
ているということではない。生の肯定感がその
背後に潜んでいるような、そんな《心情の豊か
さ》が 感じ取られるということである。そし
てこの曲を耳にする誰ものが、その情感の細や
かさや深さにあたかも共鳴するかのように、
姫女と同じような《豊かな心情の世界》に包ま
れるということなのである。
たしかに現代は、生きることの意味やその素
晴らしさを説く直接的な言葉があらゆるメディ
アを通じて私たちの前にあふれている。でもそ
の背後には”狙い”や”作為”や”思惑”が透けて見
える。そんなものはすぐに飽きられ、錆びつき
忘れ去られてしまうのがおちである。
私はそのアルバムを繰り返し繰り返し何度も
聞いていた。
そこ収められている姫女の曲が私を引き付け
たのは、当時流行の先端を走っていたところの
そのオシャレ感やカッコヨサのためではなかっ
た。ましてや、その曲のアイドル感や演歌感で
もなかった。むしろ姫女のデビュー曲のように
前の世代にうけいれられたような古さを感じさ
せるような内容だった。でも決してそれだけで
はなかったのだった。
* * * *
* * * *
さて心とはどういうものなのだろうか?
心が広いとか、心が豊かとはどういう
ことなのだろうか?
母親のお腹の中で羊水に包まれているとき、
赤ちゃんにとって外部も内部もなく、心と云う
ものもない。
音は感じているかもしれないが、それも外部
でも内部でもなく、自分が自分の心が感じてい
ると云うものでもはない。でもそのことを敢え
て心と云うなら、そのとき心と云うものは宇宙
そのものかも知れない。
その後赤ちゃんはこの世に生を受けるのであ
るが、その自らの泣き声と身体の触覚により外
部と内部の境界に気付くようになる。そして間
もなく光を知るようになる。その頃になると外
部と内部の区別がはっきりと意識されるように
なり、その内部の世界が心として意識されるこ
とになる。そして味覚や嗅覚よって、その内部
世界の意識が心としてさらにはっきりと確立さ
れていき、やがてその心は《自分》として発展
していくのである。と云うことは、心とは無限
の広がりのもとに成り立っていると考えてもい
いのではないだろうか。
物理的制約のもとで発展してきた五感の経験
によって本来無限の広がりのある心に境界や制
限を設けるようになっているのではないだろう
か。もしここで、心というものを無限の広がり
のある空間のようなものと考えてはどうだろう
か。そして人間が生きていく上で様ざまに経験
したことが、その任意のどこかに維持保管され
ると云うことにしたらどうだろうか。もしその
ことを視覚的にたとえるとしたら、例えば背丈
ほどの小山のようにである。
本来心は無限の広がりを持っているのである
から、子供のころに体験したことは、たとえそ
れがどんなに小さく些細なことでもそこに置か
れることになるだろう。そしてみじかで重要な
ことは近くに、そうでないものは遠くにという
ふうに。
やがて経験することも多くなってくると、似
た様な経験はなるべく近くにまとめられるよう
になったり、そして嬉しい経験や楽しい経験は、
より近くに、辛く悲しい経験は少し距離を取っ
て端のほうに置かれるに違いない。なぜなら出
来るだけ意識から遠ざけたいと思っているから
に違いない。でもいったんそこに置かれた限り
それが消えてなくなることはないだろう。
経験したことを示すその背丈ほどの小山のよ
うなものは、それぞれが決してバラバラではな
く、意識の元ではみんなつながっていて《自分》
として形成されているといってもいいだろう。
ほとんどの楽しいことや嬉しいことの記憶は、
何度も思い返すように、その背丈ほどの小山は
だんだん透明になり美しい結晶のように、つま
り美しい思い出や記憶になると考えてよいだろ
う。それに反して辛いことや悲しぎることは、
それほど思い返されることはなく、やがてだん
だん陰って行き、やがては光を通さない黒い塊
となってしまうだろう。
透明な小山と云うものは光を通すので影は作
らないが、黒い小山は陰を作る。とくに辛い経
験の小山は特定の場所にまとめて集められるよ
うなので、より大きな影を作る傾向にあるよう
である。
それが人間の無意識となっているようなのだ。
* * * *
* * * *
最高神の娘として姫女がこの世に誕生したとき
人間のようにすぐには泣かなかった。穏かで不思
議そうな笑みを 数秒間浮べたあと、ようやく嬉
しそうに小さく泣いた。
人間は経験によって心の無限の広がりを推し量
ることが出来るが、最高神の天性を受け継いだ姫
女はそもそも無限の心の広がりからこの世界を見
ているのである。
そして人間界に住む限り姫女の心も人間と同じ
ようにさまざまな経験によって形成されていった
のである。
ただ私たち人間と違うところは、その心の無限
の広がりによるせいか、それはまた余裕のおかげ
でもあるのだが、悲しいことや辛いことから決し
て目をそむけることなく、常に寄り添っていたの
で、そのようなネガティブな経験が心の片隅に黒
い小山としておかれ、その背後に造られた黒い影
にうごめく世界から、つまりに無意識の世界から
心をゆがめるように悪い影響を受けることはほと
んどなかった。
それゆえ最高神から受け継いだ姫女の鷹揚で開
放的な天性は決しても変わることはなかった。
* * * *
おおまかにに言って私たちは中学生の頃までは
それがどんな性格であれ、どうにか周囲との折り
合いをつけながら決定的な亀裂を生むことなく何
とかやっていけるのであるが、それ以降となると
そうも行かなくなる。
単なる性格の違いだけではなく、それぞれの持
っている才能の違いや優劣がはっきりとしてくる
からである。そしてその違いは無意識のうちの妬
みやうらやむ気持ちを芽生えさせてくる。
鷹揚で開放的な性格と云うものは、あまり小さ
いことにこだわらず周囲にも分け隔てなく接する
ので、周りからも受け入れられ評判のよいものと
されるが、それもせいぜい学校の管理が力を持っ
ている中学生ぐらいまでで、高校生にもなるとそ
れぞれの個性もはっきりとしてきて、また前述の
ような評価とはかなり違うように、いやむしろ正
反対の評価で見られるようになってくる。
例えば、「鷹揚だが、ほんとうは何かを隠して
いて腹黒いのではないか」とか、「 開放的で人
当たりもよいが、ほんとうはみんなから良い人と
思われたくて計算づくの行為ではないか」などと。
その理由としては、みんな高校生にもなると、
それまで学校などで大人から教え込まれてきたと
ころの”物事の価値や見方”とは違う”様ざまな
価値や見方”があることに気づき始めているから
である。
そこに前述のような羨みや妬みの感情が加われ
ば疑心や、心のアンビヴレンツ性から生ずるに違
いない”価値の反転”なとによって”根拠なき批判”
が生まれるのも止むをうないものとなるであろう。
青春は誰にでも訪れる。
ほとんどの者はその期間、大人が望むように
勉強に励み、そして大した悩みや問題を抱える
こともなく平穏に過ごしては、やがて社会に入
っていくのであるが、実際にはそう単純にすま
されない者たちがいることも確かである。
大人に反発するあまり、肉体的に、ときには
暴力を伴う行為でもって、大人が望むような生
き方とは正反対の行動を走り続ける者がいる。
そしてまれには、周囲との人間関係に折り合い
がつけられずに、なかなか大人の社会にはいる
準備に取り掛かれないという心の病を抱えるも
のもいる。
その心の問題の主なものは周囲に自分の思い
が伝わらないとか、大人の社会に対する不信な
どであるが、核心は自分の肉体で暴力的に大人
の社会に抵抗する若者と同じように、このまま
いけば既存社会である周囲に流されてしまい、
本当の自分と云うものを見失ってしまいそうだ
という不安なのである。それは”本当の自分”と
は”大人が望むような自分”ではないと云う本能
的ともいえる密かな確信に裏付けられている。
青春期に入った姫女は周囲に違和感を覚える
ようになっていた。
そしてときおり軋轢を生み摩擦を起こすよう
になった。
それまで天性の解放的な性格で周囲とうまく
やってきた姫女にとってはショックであった。
途惑い悩みながらなぜそうなるのか考えたが
答えはなかなか見つからなかった。
その本当の原因が姫女自身の鷹揚で開放的な
性格にあること、そして並外れた直観力や洞察
力に裏打ちされた天性の知性を本人の控えめな
性格からか人前では隠し続けたことにあること
を当時は知るよしもなかった。そしてそのこと
が姫女の心に恐れや不安を芽生えさせ、周囲の
人たちと同じように生きていても、生きている
ことが辛く苦しいものだと感じさせるようにな
り、その鷹揚で開放的な性格の基となっていた
天性の心の広がりが灰色の不透明なヴェールで
仕切られるようになり、もはや姫女の心は無限
なものではなくなっていた。
* * * *
* * * *
姫女の鷹揚で開放的な性格は周囲から誤解を
受け批判の標的となり、苦しんだが、やがてそ
れを克服できる出来事が起こった。
二十歳のとき、よくありそうな出来事を歌詞
にして、自分の才能の赴くままに作曲した歌が、
音楽祭でグランプリをとったのである。
デュオ名《あみん》
楽曲〈待つわ〉
その歌詞
かわいいふりしてあの子
わりとやるもんだねと
言われ続けたあのころ
生きるのがつらかった
行ったり来たりすれ違い
あなたと私の恋 いつかどこかで
結ばれるってことは 永遠の夢
青く広いこの空 誰のものでもないわ
風にひとひらの雲 流して 流されて
私 待つわ いつまでも 待つわ
たとえあなたが ふり向いてくれなくても
待つわ いつまでも 待つわ
他の誰かに あなたがふられる日まで
悲しい位に私
いつもあなたの前では
おどけて見せる道化者
涙なんていらない
わかりきってる強がり
平気で言ってみても 一人ぼっちの時には
そっと涙を流す
誰も私の心 見ぬくことはできない
だけど あなたにだけは わかってほしかった
私 待つわ いつまでも 待つわ
たとえあなたが ふり向いてくれなくても
待つわ いつまでも 待つわ
せめて あなたを 見つめていられるのなら
待つわ いつまでも 待つわ
たとえあなたが ふり向いてくれなくても
待つわ いつまでも 待つわ
他の誰かに あなたがふられる日まで
ここから単純に、この楽曲は姫女の自分の
経験を歌にしたと思ってはいけない。本当に
自分の経験かもしれないが、もしかしたら身
近のところでそのようなことを見聞きしてい
て知識や情報としてすでに持っていたかもし
れないからだ。
なぜなら現実はもっと複雑であるだけでは
なく、創作者である姫女の視野は常にそのよ
うな現実世界に広く注がれているからだ。
それにそう考えないとその後に生み出され
てくる多くの楽曲や、単純に歌謡曲として理
解することが出来ない難解な歌詞の展開が成
立しなくなる。
だが姫女の自分の経験と見たほうが楽曲と
してはすこぶる興味深い。この曲の歌詞を見
ると言葉もその意味も平易である。でも独立
した詩としてみるとその展開が少し飛躍しす
ぎていて少し奇異に感じる。
当時この歌を適当に聞き流していたときは
気づかなかったのだが、いま改めて読み返す
と文学詩にはありえないような巧みな情景転
換があることが判る。それはあたかも歌詞が
曲想に引きずられて従属しているかのように
も見える。でもこれは間違いであろう。その
情感のもとで混然と沸き起こる歌詞と曲想を
お互いに協力補完させあいながら発展させて
いった結果が、必然的にこのん楽曲となった
とみるべきであり、歌謡曲としては当然のこ
とであり、またここが姫女の歌がほかの歌謡
曲と違う由縁でもあり、そしてここに姫女の
天性の才能の萌芽が現れているとみることが
できる。
この天稟はその後の姫女の数々の楽曲を生
み出す本源となり支えとなる。
この歌によって姫女たちの名は全国に知ら
れた。そして”時の人”となり有名人になった。
これで夢がかない、過去に自尊心を傷つけ
られ自分を苦しめた人たちを見返すことにも
なり、その苦しみから解放されたことになる
のであるが、物事はそう単純ではなかった。
この大成功は新たな悩み苦しみを生じさせ
つつあった。なぜなら大人たちの世界からの
圧力が絶え間なく押し寄せる波のように感じ
ていたからである。
その主なものは、次なる楽曲の発表、それ
も〈待つわ〉の延長戦にあるような楽曲、と
云うのも似たような曲想のほうが同じファン
層を引き止めておくことができるだけではな
く、商売になると云うのが歌謡界の常識だか
らである。そしてこれからコンサート行って
いくためには、より多くの持ち歌が必要だか
らである。さらには二人の可愛らしい容貌か
らして、二人をアイドルデュオとして売り出
そうと画策するものもいたに違いない。その
ほうが短期的には儲かるからである。
そして実際に二人がそれらの要請に応える
ことが出来たのは、<待つわ>の延長戦にある
ような、乙女たちのゆれる恋心を歌った楽曲
だけだった。姫女たちにとってそれらの周囲
の無言の圧力は新たな苦しみとなった。
* * * *
いつのまにか姫女は成長していた。
それは心の変化によってもたらされた。
今までは(この場合少年期においては)、心
というものを記憶物の倉庫であるかのような、
あたかも広がりのある静的な空間のように扱
ってきたが、青春期になるとそのような心の
あり方に徐々に変化が起こってくる。
それは心が、外界の変化に敏感に反応して、
それに合わせるかのように、暖かくなろうと
したり、冷たくなろうとしたり、広がろうと
したり、縮まろうとしたり、という感じであ
たかも生き物であるかのように変動するので
ある。そのことが情感の揺れとなって気持ち
の表面にあわられるのである。
たとえばそのあらわれは、晩夏の夕暮れの
急に冷え込んだありふれた町並の憂愁であっ
たり、秋の夜の舗道から見える星空の悲哀で
あったりと。
そしてその個人的なものに過ぎない心の憂
愁や悲哀は、世界や宇宙の憂愁や悲哀とかさ
なり、視野は必然的に世界や宇宙へとむけら
れるようになる。
視野の広がりはただ単に眼に映る世界が広
くなっていくだけではなく、風景を見て感じ
たり思ったりすることは、さらに深くなり、
どんな些細なことにも心が動かされる情感の
細やかさの深化によって、目に見えない世界
もさらに広がっていく。
そして姫女の心は、アイドルになることで
もなく、また売れる楽曲を生み出すことでも
ないことに占められるようになっていた。
やがて周囲の要請に応えられないことや、
自分の思いが通じないことに苦しくなり、行
き詰まり、苦しくなった。それに姫女の心の
変化(成長)がそのような苦しみを和らげるよ
うには作用しなかった。なぜならそのことが
心の成長だとははっきりと意識されてはいな
かったからである。そして活動をやめ《あみ
ん》を解散することを決意した。
そして姫女は故郷に帰った。
なぜ姫女は活動をやめて故郷に帰ったのだ
ろうか?
当時姫女の周りには多くのファンだけでは
なく、姫女の並外れた才能を見抜いた慧眼の
持ち主や、その容姿からアイドルとしての商
品価値を見出して、アイドルシンガーソング
ライターとして売り出すことに実績や自信の
ある敏腕なプロデューサーなる者もいたこと
はまちがいない。もし姫女がこれらの情況を
容認すれば、その才能の発揮によって、少な
くともその後の長きにわたる、楽曲の提供や
自らのコンサートなどによって、歌謡界に安
定した地位や名声を保持しえたことは間違い
ない。
だが姫女はその道を自ら閉ざした。
なぜなのだろう?
でもこれ以上そのことを詮索することはふ
さわしくないようなきがする。
なぜなら姫女はその後カムバックによって
再び栄光を取り戻すことになるのであるから。
* * * *
やがて自分が本当にやりたいことに気づい
た姫女はシンガーソングライターを目指して
再び上京した。
故郷に帰っていたとき姫女は後悔の念にさ
いなまれた。もう少し周りの言うことを聞い
てアイドルのような活動をすればよかったの
ではと、そしてもしそれがだめなら周囲が求
めているような楽曲に自分の才能を賭けて見
ればよかったのではないかと。自己演出の苦
手な姫女にとって、そのことに応えることは
所詮無理なことではあったが、でもそれだけ
ではない。この頃は、姫女は、どのような曲
想がが、そしてどのような歌詞が盛り込まれ
れば大衆に受けて流行るかと云うようなこと
には、うすうす感じてはいたが、姫女自信が
本当に作りたいものは自分の心に誠実に向き
合いながら、そこから生まれてくる真実の思
いや情感が、正直述べられた楽曲だというこ
とには、まだ確信の持てるのあるヴィジョン
として描けていなかった。
青春前期、姫女は周囲の理由なき批判に途
惑い、その開放的な性格はぎこちなくなり、
透明だった心はかげりを見せるようになって
いた。だが姫女はそんなときでも自分の心を
見つめ対話することを決してやめなかった。
それによって楽しい出来事や嬉しい出来事
は、いつでも思い出せるようにはなっていた
が、同時に辛い出来事や悲しい出来ごとにも
寄り添いながら、なぜそうなるのかを自分な
りに考え分析をしたりして、決してそれらを
心の奥のほうに追いやって無視してしまうと
いうようなことはしなかった。
そのことは苦しさや辛さが長引くことでも
あったが、誠実で隠し事ができない姫女にと
って、それはごく自然なことだった。 でも
そのことによって自分がなぜ批判され誤解さ
れる理由がわかったというわけではなかった
のだが。
そのころまでに姫女にとって何気ない風景
でも、それまでの単なる写真のように美しい
ものとしてだけではなく、心に何かを訴える
情景となり、そこに寂しさや憂愁を感じるも
のになっていた。
また人々の何気ない日常生活にも、深い共
感や思いを馳せる対象になっていき、そこに
はかなさや悲哀を感じるようになっていた。
そして以前の乙女の恋心を穏かに歌ってい
たことろは比べ物ならないくらい心は豊かに
情感は深くきめ細やかに、そして複雑になっ
ていた。
だからあくまでも自分の心に誠実であろう
とする姫女にとって、もはや計算されたよう
な楽曲を創作するような余裕などなかった。
故郷に帰っている間に姫女は自分の心の変
化と成長にはっきりと気づいた。
そして理解した。自分が本当に作りたいの
は自分の心に誠実に寄り添い自分の気持ちに
正直に従いながら心の奥底から湧き出る真実
の思いや情感が表現された楽曲であるという
ことに。
そして不安と、それをも凌駕するようなひ
そかなな自信を覚えながら上京を決意したの
であった。
* * * *
姫女の性格は見ためどおりに鷹揚でしかも
開放的で楽天的である。
それで”もしかしたら自分を主張しない意志
の弱い女性ではないか”と思われがちなのであ
るが、実際はかなり違っていて、意志はかなり
強く周りから見たら頑固と思えるくらいに自分
を曲げない。そのためあらぬ誤解をうけて批判
されたりするのである。
それから自分の意見を持っていなさそうに見
えるのも間違いである。持ってはいるが積極的
に言わないだけのことである。なぜならそのこ
とが真実であるかどうか、まだ自信がないから
である。それは真実を求め続ける姫女にとって
は当然のことであった。自分を目立たせたいが
ためにしゃべり散らす人間とは大違いである。
姫女の意志の強さは最高神の天性を受け継い
でいるせいかかなり強固である。そのことはそ
の後さまざまな楽曲にちりばめられ星のように
輝くことになるのである。
そして姫女は外見以上に聡明で洞察力に優れ
ている。ただなぜか姫女はそれを表に出さなか
った。それで人間観察に鋭敏な者から見れば、
姫女はそのことを隠してあえて謙虚に振舞って
は大人しそうに見られたい”ぶりっ子”に見える
かもしれない。
才能があるのに、ないように見せることはと
ても鼻につくことで、他者から見ればそれは小
ばかにされているように感じるのである。でも
だからと言ってそのことに姫女は負い目を感じ
る必要はないはずであった。なぜなら、やがて
は最高神の愛娘として迎えられるときが来るの
であるから。
そもそも控えめで大人しそうに見えるからと
いって、その人間を自分の意見を持たない意志
の弱いものだち決めつけるのは間違いであろう。
いやむしろその逆であるというのに。
男でも女でも人は青年前期までにその異性の
理想像を完成させている。というのもほとんど
無意識のうちに形成されているといってもいい。
それはその人の体験や性格によって様ざまで、
イメージと云うよりも概念的なものに近い。
なぜなら具体的なイメージ像よりも概念的なも
のの方が確実でしかも豊かで長持ちがするから
である。
姫女にとっての男性の理想像はつねに漠然と
しているが、〈待つわ〉に登場して以来、その
理想像は変ることも衰えることもなく姫女の心
に生き続けることになる。
* * * *
* * * *
シンガーソングライターを目指して東京で
新生活を始めても、すぐには創作活動に入れ
なかった。新生活に慣れていないこともあっ
たが、物に触れて心に沸き起こるものだけを
作品にしようと考えていた姫女には、まだそ
のようなものを生み出す心のゆとりが生まれ
ていなかった。それでしばらくは、このまま
何にも生み出せなくなるのではないだろうか
という不安に苛まれる毎日が続いていた。
ちょうどその頃、孤独に苦しむ愛娘を見て
いた天上の最高神は、何とかして助けてあげ
たいと思った。
そして音楽をつかさどる女神ムーサを地上
の姫女の元に舞い降らせた。
女神ムーサは姫女に寄り添うようになった。
そして女神ムーサはそのときを見計らい姫女
自身も気づいていなかった”神性の扉”をゆっく
りと開いて姫女の心と体をその光で満たした。
やがて姫女は新生活になれたこともあり
それなりに作品を生み出すようになった。
* * * *
* * * *
姫女の作品はその傾向から次のように大別できる。
(1988年までに発表された初期アルバムから)
[大人の女性の恋愛とそのやさしい破局]
〈風は海から〉
メルヘン的な情景から触発された大人の
破局劇だが、きっとあるだろうという思いと、
まだ自分はそういう世界には入り込めないと
いう思いが重なり合って作り出された情感が
穏やかに描かれている。
東京に来て初めての曲とされているが、
自分の心の動きに誠実な作品であることは
変わりない。
〈夏の日の午後〉
窓を開け、その夏の日の午後のさわやかな
空気を吸い込んだ瞬間に、その曲調も歌詞も
すべて頭に浮かんできたような作品である。
ここに出てくる男性の理想像は〈待つわ〉
の頃よりもだいぶ変容して大人びたものに
なっている。
本人も単純な恋心では終わらない視野の広
さを見せている。
それでもそのような恋愛に応え切れない
現在の自分を重ね合わせながら少し悲哀を
感じている自分を揶揄している。
そしてのちの”夢をあきらめないで”へと
つながっている楽曲となっている。
〈見送るわ〉
どんなものにも変えても大事な愛がある
と言いたいのだが、なぜかそのことで惑う、
でも時代は変わってきている、女たち自身
にも変わることを求められているのだから、
思い切って決断してはと、珍しく強気にな
った姫女が 周囲の女性たちに語りかける。
この曲から私は、普段遠慮がちに歩いて
いる姫女が胸を張って凛々しく人ごみを歩
いている姿を思い浮かべた。
〈あなたと生きた季節〉
この曲について姫女自信のこんな覚書がある。
(恋はいつもいつも終わるのだろうか。
無限に続く時間の流れの中で、無限に広が
る宇宙の地球という星で、出会ってしまった
偶然には、いったい、どんな意味があるのだ
ろう。そして、もっとやさしくできたはずな
のにという後悔さえたどりつけない場所に、
ふたり別れてしまった偶然には・・・。
はかなく消えていくものばかりが、よぎる)
いつしか姫女の恋愛には永遠の時間や無限
の宇宙が かかわるようになっていたのだ。
最高神から受け継いだ天性からすればそれは
当然のことなのだが。
〈白い夏〉
あまりにも穏やか過ぎる浜辺の風景が広が
っているというのに。でも穏やかにはなれな
い恋がどれほど破れていったことだろうか、
そしてたぶん私だったらこんな恋の終わりを
迎えるだろうと、穏やかすぎる風景に溶け込
かのむように姫女は静かに思いをめぐらす。
彼女の作品はどんな楽曲でも曲調と歌詞と
歌声の調和を見てとれる。
これらの楽曲は、海や町並みや夜空など
の日常の何気ない風景に、時代の様ざまな
恋愛模様に触発された姫女の情感を重ね合
わせた曲想となっている。
これらはまた大衆受けをする流行歌的色
採が強いが、姫女は決してそれを狙った訳
ではなく、あくまでもデビュー以来ずっと
続いていて、そしてその後も途切れること
なく続くことになる、姫女にとっては最も
感情移入のしやすく、そして最も得意とす
る恋愛情趣が歌われているに過ぎない。
[大人の女性の恋愛とそのこだわりのある別れ]
〈美辞麗句〉
ここには姫女の並外れた他者への共感性が
表れている。
とくに同年代の若い女性の心の不安定さや、
感情の両面価値性に姫女自身もそんなに違っ
ていないということを暗に知らせようとして
いる。
〈雨の町〉
この曲を作りながら同世代の女性たちにあ
たかも自分のことのように感じる姫女は思う。
素直になれないというだけでこんな別れ方
をする男女はこの世に無数にあるだろうと。
〈私はここにいる〉
好きな人の前で自分をうまく表現できない
のは何も女性だけとは限らないのだが。とく
に好きであればあるほどかみ合わなくなり、
どん逆の方向にすすんでしまう、どうしょう
もないものなのだが。そんな人たちに姫女は
みんな同じようなものよと、心から同情する。
〈クリスマスの夜〉
時代はバブル前夜。
姫女はクリスマスの夜に華やかな
歩道をさびしそうに
独りで歩いている若い女性が目に
付いたのだろうか?
男女の無数の出会いと無数の別れ、
そのたびにメソメソしてはいられない、
そろそろ道を示さないと、
と姫女は思い巡らす。
[大人の女性の恋愛とその屈折した別れ]
〈Baby,Baby〉
女性は大人になったと思っていても、ときに
は感情に任せた少女のように言動をするときも
ある。
そうなったらおしまい、後は別れることしか
ない、でもそうなるとあとで理性的な女性に戻
ったときに後悔もする。
でももう、少女のように泣きじゃくるように
ことはしない大人なのだから。
もうすでに姫女の眼には地平線の向こ
う側にちらついている恋愛の現実の姿がはっき
りと見えている。
〈ドラマ〉
この時代の女性の生き方に姫女はどのくらい
影響を受けていたのだろうか?
多少の未練があっても決断する勇気の必要性
を説く。
曲調は紛れもなくその勇気を応援している。
まるでドラマにあるように。
姫女はどんな曲でもその曲想に合うように、
メロディーと歌詞と声を調和させて曲作りを
している。
そしていつもその完成度は高い。
[遊び心の大人の恋愛]
〈ピエロ〉
恋愛に揺れる乙女心を懐かしむかのよ
うな楽曲。
こんなにも軽快な流行り歌風のものも
作れるんだよという多能さを示している。
姫女に余裕が出てきた証拠でもある。
〈月が泣いた夜〉
この曲も姫女の多能さと余裕から生まれ
た作品である。
〈見返してやるんだわ〉
ちょっとした誤解や行き違いから破局
していく恋人たちの例を姫女は多く見聞
きしていたに違いない。
こんな女性たちの屈折した心理にも心
から共感できる姫女はきっと笑みを浮か
べながら楽しむようにこの曲を書いたに
違いない。
[ドラマ的恋愛の表現]
〈煙草〉
〈一人息子〉
〈冷たい雨〉
これら三曲はそのままドラマになりそうな内容。
最後に〈冷たい雨〉にはそれまでにはほとんど
無かった男性の理想像に変容が見られるが。
[感情の生々しい表現]
〈砕ける波に〉
姫女には珍しく自分の感情を
そのままぶっつけたような作品。
心の広がりもなく冷たい情感があるだけ。
まさに聴くものの胸を氷の剣で
突き刺すような作品。
神性さのかけらもない。
〈ついてない〉
これも前項と同じような作品。
姫女の曲にはどんなに絶望的なことを
歌っていても、
必ずそこには救いや希望の光が
見え隠れしているものであるが、
この曲にはその希望の光が見られない
真っ黒な絶望があるだけ。
だがこれは姫女の心の奥の奥に普段は
見えないように潜んでいて、
誰かに泣き叫びながら訴えたかったほどの
辛さや苦しみであったのかもしれない。
* * * *
このとき父なる最高神は、わが娘が作った
とは思えないこれらの楽曲を聴いて、これは
きっと娘の身に何か異変が起こっているに違
いないと思い心配になった。
そこで母である《夢の国の女王》に訊ねた。
最高神
「これはいったいどういうことなんだ。女神
ムーサは何をしているんだ。神性の扉は開か
れていないのか?」
夢の国の女王
「もう開かれております。それに神性の光に
包まれてながら作られたような楽曲もすでに
出来上がっております。ですから何の心配も
無いと思います」
最高神
「でも、この凍りつくような絶望感はどうい
うことなのだ」
夢の国の女王
「それは、ですね、、、とにかくあの娘は
自分の心に嘘がつけないんです。これまで
いろんな辛いことがありました。誤解や根
拠の無い理由で批判されたり、なかにはあ
の娘の成功をねたむあまり、わざと冷たく
当たったりするものもいました。そのたび
にあの娘は深く傷つき、自分は何か悪いこ
とでもしているのだろうかと悩み苦しみま
した」
最高神
「そうだとは知らなかった。才能に恵まれ
ている娘だから、成功するのも当たり前、
みんなから賞賛されるのも当たり前、それ
で幸せだとばかり思っていた」
夢の国の女王
「人間の世界は思った以上に複雑ですから」
最高神
「そんなつらい思いをしていたなんて、
知っていたら連れ戻したのに」
夢の国の女王
「でもあの娘は絶対に弱音を吐きませんで
した。想像以上に芯のしっかりした娘です。
逆境をも自分の生きる力に変えていくよう
な意志の強い娘なのです。『安定に腰を落
ち着かせるのは好きでない』などと強気な
ことを言っているくらいですから。実を言
うと私も本当は心配でした。あの大成功の
あと自分の才能を生かして、そのまま音楽
界に残っていれば、どんなに楽かと思いま
した。でもあの娘はそんな過去の栄光を投
げ捨て零から再出発する道を選びました。
そして今再びその栄光をつかみつつあるの
です」
最高神
「それにしてもあういう曲を聴くと心が締
め付けられるようになるよ、救いのない絶
望感だけしかない」
夢の国の女王
「大丈夫です。もう心配は要りません。
先ほども申しましたように、あの娘はとに
かく自分の心に嘘がつけないだけなのです。
あの娘は良いことも悪いことは楽しいこと
も辛いことも、全部自分の心に留め置くの
です。そして良いことや楽しいことは対話
をするように何度も思い返したり、そして
悪いことや辛いこととは何とか折り合いを
つけようと何度も何度も思い返しては対話
を試みているのです。普通人間は辛いこと
や苦しいことは二度と思い返さないように
心の片隅に追いやるようにして閉じこめて
しまうものですが、父なる最高神の天性で
ある開放的な心を受け継いでいるあの娘に
はそのようには出来ないのです。開放的な
心を持ったあの娘は幼いときから自分の心
と真正面から向かい合い、見つめ、そして
対話を続けてきました。そのため自分の心
の陰りや曇りをそのままにしておくことが
出来なかったのです。その陰りや曇りに光
を当ててやることが、自分がその暗い思い
出から解放されて、うそ偽りの無い本当に
開放的な心の持った真実の自分になれるに
違いないと感じていたからです。ですから
あのような絶望的な曲はあれが最初で最後
になるでしょう。これであの娘は神性の眩
い光を放つような楽曲をどんどん生み続け
ることが出来るでしょう」
* * * *
* * * *
[誠実であるために起こる愛の不安]
この頃になると次第に姫女の秘められた
天性が発揮されるようになる。
その秘められた天性とは楽しさや喜びだ
けでなく哀しみや寂しさを同時に感じるこ
とができるような感性。
そして若者の誰もが体験する人生や未来
に対する不安や苦悩をまるで自分のことの
ように感じることのできる並外れた他者へ
の共感性。
〈Today〉
姫女にとってかつて憧れの対象だった男
性たちが現実の世界で敗れ去っていくこと
はとても悲しいことだった。
どのような男たちが敗れ、どのような男
たちが勝ち残っていくか、姫女には痛いほ
ど判っていた。
そして姫女はそういう男たちを周囲の女
性たちが必死に支えてあげることをただひ
たすら願う。
〈微風〉
敗れ去り自信を失っていく男性たちを救
うことのできない無力さそして悲しみのき
わみが歌われる。
神性の光に照らされて生み出された歌詞
”悲しいほどひたむきに”
現代社会において果してどれほどの人間
がこの歌詞の深すぎる意味に共感できるだ
ろうか?
〈迷路〉
姫女自身の絶望ではなく、理由も知るこ
となく敗れ去る男たちを救うことも出来な
い恋愛の迷走と無力感に姫女は絶望する。
そして自分に出来ることは周囲の女性た
ちがそんな男たちを最後の最後まで支えて
あげることを祈るだけ。
ここに登場している躓き苦しんでいる
男性像は、バブルの波を華麗に泳ぎ渡っ
ている成功者のそれではなく、たむきに
人間として生きようとしている、半ば姫
女自身が投影され、それまでに理想化さ
れていた姫女自身の男性像でもある。
[姫女自身の生き方への願い]
〈五月の晴れた日〉
どんなに自分に正直に生きていても悲し
みが消えてなくなることは無い。なぜなら
この宇宙の重みは悲哀によって支えられて
いるから。
このことを心の奥底で受け止められた
とき”夢をあきらめないで”につながって
いく。
〈輝き〉
まさに神性の光が輝いているもとで作ら
れた楽曲。
数々の絶望を乗り越えた今、
これからどんな苦難が訪れようと、
必ず乗り越えることが出来るという
自信と決意に満ちている。
これはその神性さが最も強くあらわれて
いる”Beleive”へとつながる。
〈私の空〉
町の風景に押し寄せる憂愁。
どんな些細にことにも心が揺れる小さな自分。
悲しいのは自分だけではないと判っていても、
崩れ落ちそうな自分、そしていつか大きな翼
で羽ばたく日を夢見て、必死に自分を持ちこ
たえようとする。
〈リベルテ〉
いまだに些細なことに躓いたり転んだりし
ている私だが、でも自分の心そして他の人た
ちの心も信じて勇気を持って生きていけば、
きっと未来は開けるはずだと姫女は揺れる心
に不安を感じながら必死に決意する。
〈未知標〉
思い出にいざなう不安な夜に思う。
今は幼い日の無邪気さも青春が始まった頃
の快活さも無い。こんなはずじゃなかった
と。青い空を翼広げ羽ばたいていた自分の
姿は幻だったのかと。
こんな作品も前に進むためには必要
だった。
これは<あみん>時代の作品であるが、このよ
うな芽生え始めた不安は、復帰後の楽曲に具体
化され様々な形で現れている。
もちろん姫女はこの後もずっと自分が
最高神の愛娘であることを知ることは無い。
大きな翼など望めばすぐ手に入るというのに。
* * * *
時代はバブル、売れる曲を作れば
天下を取れるというのに、
それでも姫女は自分の感じる心を
大切に曲を作りつづけている。
[愛の喜び]
〈ソレイユ〉
理想化されすぎた男性像の理想化された
女性像として生きる事が愛の最高の喜びに
違いないと夢想する。
これはのちの〈夢の途中〉へとつながる。
[やさしすぎる愛]
〈秋の日の夕暮れ〉
白昼夢のごとく永遠の愛を夢見る。
もし永遠の愛があるとしたらきっと
こんな風だろうと。
それにしてもやさし過ぎてひたむき
過ぎる。
それは従来のような献身でも自己犠
牲でもなく新たな愛の形地平の出現を
予感させる。
このあまりにも穏やか過ぎる歌い出
しは、瞬時にして聴く者の心を魅了する。
姫女の曲にはこのようなものが多い。
それは何の加工も加えることもなく会
話をするときのようなおだやかな声で歌
っているからである。
このような優しく語りかけるような
歌声に私たちは無限の癒しを覚える。
* * * *
* * * *
生き物の究極の目的と価値は生殖と
時を超えてのその命のつながりである。
でも思考能力を獲得した人間は
その先へと進化してしまった。
理想的な異性像とその理想像との関係性
をイメージすることである。
その新しい目的と価値は私たち人間を
永遠の青春へと導いてくれるはずのものなのだが。
* * * *
* * * *
[神性の波動に揺られながら]
〈電車〉
何気ない風景に心が動かされるとき、
姫女にとってそれは情感となり、その
情感は言葉となってあふれ出し、やが
て言葉はメロディーにつながり、
そしてひとつの楽曲となる。
新生活を始めた頃、きっとこんな風景
を電車内で見たに違いない。
そしてその女性の境遇が今の自分とそ
っくりに違いないと知る。
このとき人並みはずれた姫女の他者へ
の共感性が胸からあふれ出す。
きっと私と同じようにうまく行かない。
きっと私と同じように将来が不安。
きっと私と同じように過去と決別でき
ていない。
そしてきっと私と同じように孤独で
後悔にさいなまれているにちがいない。
でも結局は、未来を開くことが出来る
のは自分しかいないということに
気がつく。
自分の心が気になると人は誰でも孤独
になる。
そしてその孤独の道を歩みえざるをな
くなる。
姫女の心に芽生え始めるひたむきな勇気
とひそやかな決意によって、絶望的な曲想
にもかかわらずかすかに希望の光を感じ取
ることができる。
飾り気の無い心がそこに現れているとき、
それがどんなに絶望的に見えようとも希望
に支えられている。
(歌詞)
”あなたを失くしてまでも決めた道を”
この小節にいたると男の私でさえつい涙ぐ
んでしまう。
そして姫女の真の正体を知る。
もし私が天の父なる最高神だったら
「そんなにつらい思いをしているんだったら」
と言ってきっと姫女を連れ戻すだろう。
〈今日も眠れない〉
気負うことなく書かれた歌詞を追ってみよう。
”見えるものを
見えるといえない
ことが多すぎて “
姫女は自分が感じることがほかの人と
どこか違うことにずっと気づいていた。
でもそれをそのまま表現してもいいも
のかどうかいまだに迷っている。
他の人はみんな自分の意見をもっていて、
そのことに自信を持って生きているのに。
これは歌謡詞というより詩に近い書き出
しである。
”誰も彼も利巧に見えて
今日も眠れない”
私はとっさに生涯青春(夢を見ていた)
だった石川啄木の短歌を思い出した。
石川啄木(歌集一握の砂から)
”友がみな
えらく見ゆる日に
花を買い来て
妻としたしむ”
”ああ遠く離れて人ごみの中誰かさがしている
しばらく電話なんかしないでよせつなくなる
思い甘えられるあの人に帰りたい”
この歌詞の”あの人”とは男性の理想像に
なるのだろうが、実際誰でもよい、信頼で
きる友達でも、ふるさとの家族でも良い。
大事なのは誰もが孤独に苦しむときに、
誰かに頼りたいという切実な思いが表現さ
れていることである。
そしてこれが普遍的な情感として人々に
共有され感動を呼び起こすのである。
そして歌詞は文学の詩のように展開する。
”崩れそうな私を支えるものは
悲しみといつになればかなうか
わからない夢の数々”
崩れそうな自分を支えるものは”悲しみ”、
何故”悲しみ”が自分を支えることが出来
るのだろうか。
おそらく姫女はこのときまでに、宇宙
の重みを支えているのは悲哀であること
がわかっていたのかもしれない。
”ああ出来ることならいつも
誰かのそばにいたかった”
と一瞬女性らしい弱気を見せるが、
すぐに反転する。
“しばらく電話なんかしないでよ帰らないわ
いつの日かあの空を駆けめぐる鳥になる
ああ闇が私を包むそのときにもきっと迷わない
輝く瞳だけは失くさないでいきたいから
いつの日かあの空を駆けめぐる鳥になる”
そして最後は高村光太郎の詩”道程”のよ
うな気迫と決意を見せながら孤独や苦悩か
ら解放された自分を夢見るる。
だがこの最後のリフレインは、姫女自身
だけではなく、この歌を聴く誰もがその天
空の高みへと導かれ開放された自分を夢見
させられているのである。
姫女は圧倒的に若い女性たちに
支持されていたという。
でも私は女性でもなければ若く
もない、初老の男だ。
それなのにいつ聞いても感極まり
泣いてしまう。
〈夢をあきらめないで〉
もしあの日テレビを見ていなかったら、
そしてエンディングでこの曲が流されて
いなかったら、当時姫女はほとんどマス
メディアに取り上げられることは無かっ
たので、私は生涯姫女を知ることは無か
ったであろう。
その頃の私にとって音楽というものは時代
の背景として、さらに影薄く後退していた。
つまり歌が、私のこの社会に対しての帰属意
識を維持するために、集団性や共同性の意識
を呼び起こす役割を既に失っていたというこ
とである。
その最大の原因は業界の売れれば良いとい
う商業主義と、その歌の背後にある狙いや作
為や思惑に飽き飽きして何の興味もわかなく
なったからであろう。
それはまた同時に、私自身が社会に対する
帰属意識を何か他のもので見出していたから
に違いない。
それは、それまで私を苦しめていた生きる
ことへのぼんやりとした不安や不満に変わっ
て、これからの自分の人生に対して確固とし
た目標や自信を獲得し始めていたということ
でもある。
言い換えればそれは四十前にしてようやく
社会とも折り合いが付き、そして自己の内奥
から芽生えば始めた”俺でも生きられる、俺で
も生きていいのだ”という生の肯定感が芽生え
始めたということなのである。
この歌の歌詞だけ見ると何となくまとわりの
なさを感じる。でもこれは前述のようにその情
感のもとで混然と沸き起こる歌詞と曲想をお互
いに協力補完させあいながら発展させていった
結果が必然的にこの曲となったとみるべきであ
ろう。
そしてこの曲は聴くものを魔法にかけるよう
に始まっている。
後に知るところによるとこの曲は失恋の歌で
あったそうだが、でも、別れる者が好きな人で
も、友達でも、家族でも誰でもかまわない、
そのくらいこの曲は普遍性を持っているのだ。
というのもこの曲がほんとに失恋の歌なら、
喪失感や悲壮感が漂っていてもいいはずなのだが
少しもそんな気配はない、むしろ逆であるからだ。
そして魔法にかかったものはすべて夢見るよう
に自分の心がまるで希望の光にみたされながら、
とどまることなく広がり続けるのを感じる。
やがて自分が心情の豊かな世界に紛れ込んで
いて、何か超自然的な愛に支えられているような
自己肯定感に満たされながら幸せな気持ちになる。
だれもが未来社会や人間存在を無条件で肯定す
る心情の豊かさに包まれたいと願うからだ。
〈Believe〉
この曲について語ろうとするとそう簡単では
ないことが判る。
私はこの曲をしばらく聴いていない。意識的
に避けているといってもよい。というのもこの
曲にはどんな逆境や絶望に陥っているものでも、
そこから救い出してくるという力が、神々(バッ
ハのような)しさがあるからである。
最初にこの曲を聴くものはだれでも、人生に
ほとんどの人が体験するであろう失敗、挫折、
絶望、決別、離反、失意、後悔の念などが歌わ
れているように感じるが、曲が進行するにした
がって、実際の内容は、それらに負けまいとす
る強い意志、決して諦めない勇気、ひたむきな
努力、ひそかな決意、そしていつも目の前に広
がっている壮大な宇宙に支えられた未来への希
望が歌われていることに気づく。
そしてその希望の光は、これらの数々の苦難
を乗り越えたあとには喜びに満ちた充実した生
活が待ち受けていることを暗示しているだけで
はなく、誰にもおとずれる死も、決して私たち
の終わりではないと思わせるほどの輝きを放っ
ている。
だから私は最期の時にはこの曲を流してもら
うだろう。なぜなら私はそのとき自分の人生を
振り返ってはあれやこれやと後悔しているに違
いないからだ。でもこの歌で慰められ穏やかな
気持ちになって死を新たな旅立ちとして迎えて
いるに違いないから。
この曲は姫女の二十代後半の作品である。
どれほど人生経験が豊かだったのか?
でもこれも姫女の神性のなせる業であろう。
* * * *
宇宙本質は静寂とおだやかさである。
そしてその重みは悲哀に支えられている。
* * * *
芸術において傑作が生まれるのは、
その芸術家が今度は傑作を作ろうと
思って作るから傑作となるのではない。
真性の芸術家なら、それをこともな
げに無意識ともいえるくらいにあっさ
りとやることができる。
そこには狙いや作為や思惑が忍び込
む余地はないからだ。
姫女は紛れもなく真性のシンガーソ
ングライターである。
そして姫女姫女これらの曲によって
再び脚光を浴びるようになる。
メディアの最前線に出てくることは
無かったが誰もがこのことを喜び応援
した。
芸術家にとって自分の作りたいもの
を作って社会に認められるということ
は至上の喜びであり最高の栄誉である。
* * * *
* * * *
[アルバムオー・ド・シェルから]
これらの作品から、この頃には、かつ
て自分の性格が絶滅危惧種のように扱
われ、ネグラと揶揄され、少しはコン
プレックスになっていたが、もう本来
の自分のままで良いんだと思うように
なってきていることがわかる。
それは再起をかけて書き上げれれた
楽曲が多くのファンに支持されるよう
になり、それによって今の自分に自信
が持てるようになったためである。
そこには自分自身を勇気付けるよう
な歌詞にもはっきりと現れている。
それらの言葉は新しい希望の光を受
けながらときには穏やかに、またとき
には凛々しく歌われる。
〈長い時間〉
”だめな生き方でも良いから私らしくいたい”
”ありのままの自分を見つめているから”
〈虹を追いかけて〉
”素直なときめきで
ほんとの自分を取り戻したい”
”素直なやさしさで
ほんとの自分を取り戻したい”
これらの言葉に解説は要らない。
ただひたすら耳を傾けるだけだ。
ここで大切なのは、これらの言葉を姫女
は自分自身にだけ向けて発せられたのでは
ないということだ。
豊かな心情の緑の沃野に、楽しさや喜び
だけではなく悲しみや寂しさを同時に感じ
ることができる心の窓を開け放っては自分
だけではなく、周りの者たちの未来や人生
に対する不安や孤独感に苛まれながらも、
どうにかその苦痛から開放されんがために
吹き抜ける風になろうとたたずむとき、
言葉がメロディーを伴って汲めども尽きな
い泉のように彼女の肉体に湧き出てきたの
だが、、、、
そしてまだまだ姫女の夢想する悲恋物語
は続く。
〈オー・ド・シェル〉
〈それぞれの明日〉
〈ジュ・テーム〉
〈愛がほしい〉
何故このような曲が姫女には多いのだろう
か。もしかしたら恋の成就は、”夢の終わり”
そして “青春の終わり”であることを無意識
のうちに感じ取っているからかもしれない。
そして幸せからは何も創造されないという
ことも。
満たされぬ気持ちや幸せでないと思う気持
ちが創造の原動力となっている。
〈青い風〉
そんななかで自分が青春に距離を持ち
始めていることに気づく。
〈リフレイン〉
それでもときには幸せに満ちた愛を
夢想するときもあるようだ。
そして穏やか過ぎる風景のもとで、青春
の悲哀が情感となってあふれるように胸から
ほとばしる。
〈愛を守りきれなくて〉
”平凡すぎる幸せよりも
何かを求めていたかった”
”ごめんね愛を守れなくて
私はもうもどれない”
情況は違うがきっと誰もがこんな思いを
したことがあるに違いない。
そして知っている、この世では最も愛する
もの同士はいっしょに暮らすことは出来ない
ということを。
この曲を聴いていると私は涙がにじむ。
なんてことだ。こんな初老の男が、こんな
小娘に慰められるとは。
この曲のなにげない歌いだしは、私たちを
進化した新たな宇宙の本質へといざなう。
銀河の生成や消滅を見ていると
その荒々しさや壮大さから、
宇宙の本質はその激しさや力強さに
あると思いがちだあるが、
それは見せ掛けに過ぎない。
なぜなら宇宙はより細やかなもの、
より繊細なのへと進化していることは
紛れもない事実なのだから。
冒頭に述べたとおり宇宙の本質は
静寂であり穏やかさである。
それを具現化しているのは私たち
生き物としての人間である。
私たち生き物はより微弱な電気信号でも
生きられるように進化してきた。
そして心はさらによりかすかな電気信号でも
その世界を形作ることが出来るように
進化してきた。
その結果心をさらに穏やかに繊細に
やさしく柔和に進化してきた。
宇宙の本質を体現する最高神の愛娘として、
そのことが具現化された姫女は、まさに
その進化した本質を自らの身を持って体現
しながら、その新たに創造された豊かな
心情の世界を楽曲として表現し続ける。
* * * *
真正の芸術家は自分が作り出すものが他者
にどんな影響を与えるかは無自覚でありしか
も判らない。
言葉から感動を生み出すことは出来るが、
感動を言葉で言い表すことは難しい。
私は今困難に直面している。姫女の歌から
受ける感動を言葉にすることに限界を感じて
いるからだ。
美辞に頼ればいいのだろうが、それだと真
正の感動からますます遠ざかる。
音楽の感動には、音が本源的に持っている
その共同性や共感性が重要な役割を果たして
いるのは間違いないが、それだけではない。
歌詞も重要な役割を果たしていることは間違
いない。かといってそれを文学の詩のように
分析しても答えは得られそうもない。
歌における歌詞はあくまでも曲想に従属す
るものであるからだ。するとやはり芸術の成
り立ちまでさかのぼって論及するべきかもし
れない。それは冒頭にある、”芸術は人間の
精神活動によって生まれるが、その根源は不
合理性や反自然性や非現実性にある”という
ことである。
私たち男女は恋愛において最終目標とする
のはその成就である。目にも見え手でも触れ
ることが出来る全き現実性である。
これまで姫女には何曲かの愛の喜びを歌っ
た作品がある、だがどれも成就はしていない。
成就するまでのまた成就した後のことを喜び
を持って思い描いているに過ぎない。それは
夢想であり現実ではない。それは非現実性が
どれほど私たちの想像力を掻き立てて、喜び
に満ちた夢を見させるかということを示して
いる。
そしてそのことを本能的に捉えている姫女
はいかに人間離れをしているかということだ。
そして私たち凡人は姫女の情感に心から
共感する。
* * * *
[アルバムKissから]
姫女を照らし始めた神性の光はさらに
その輝き増し始めている。
これまで姫女を苦しめるように立ちは
だかってきたさまざまな困難のために、
まるで地獄の季節をかけ抜けるように走
り続けてきた姫女の前に、もう障害とな
るものは何もなくなったからだ。
〈心の草原〉
追い求めてきた理想像に自分は決して
遠ざかっていないということを確信しな
がらそのことに幸せを感じている。
心がはずむように、歌詞はこれまでに
用いられた幸せを呼び込むような語彙が
ちりばめられている。おそらく最後まで
笑みを浮かべながら完成させたに違いない。
〈終わらない夏〉
愛の成就を願う喜びにあふれているが、
でもその先のことは誰にもわからない。
これで充分なのだ。恋愛の歌は。
これだけで多くのものに夢を見させ人
生に希望を持たせ幸せにする。
〈Kiss〉
誰もが理想の生きかたや理想の自分を
見つけるのは難しい、
ささやかな誠実とひたむきな心という
だけなのに、それさえも、、、でも穏や
かな風景が私を支えてくれるのだから、
迷いながらも前に進む自分を心から祝福
できる、と歌う。
〈満潮〉
これも前々述と同じように、
愛の成就を願う喜びにあふれているが、
でも実際のところ本当は誰も関心がな
い。関心があるのは成就へと向かって
いるその夢のような瞬間に多くの者が
美しさや喜びを感じながら自分の人生
に希望を抱く。
〈空のかなたまで〉
ハッピーエンドになるドラマのクライマ
ックスに流れているような音楽。
姫女の多彩振りを示す曲。
これ以上言葉は要らない。
〈青い日々〉
朗々としたこの歌声の気高さは
いったいどこから来るのだろう、いつ聴い
ても涙がにじんでくる。
静かなる青春の肯定、
そしてひたむきな人生の肯定。
〈あの海に帰りたい〉
雨の日の沈んだ情景に失った恋物語を
重ね合わせる。
姫女自身の体験というよりも、そんな
寂しげな女の心象風景を推し量ったのだ
ろう。
いずれにせよ姫女の想像力の豊かさを
物語る。
〈天使たちの時〉
まさに今にも愛が成就しそうだが、
それはその瞬間に限りなく近づいて
いるだけで、決してそこに達するこ
とはない。
でもこの曲を聴くものは、夢見る
ようにその瞬間を思い描き幸せな気
分になる。つまり音楽によって姫女
に魔法をかけられたのである。
〈adieu〉
こんなあっけらかんとした別れた方は
現代はめづらしくない。
ダンスが苦手な姫女も踊りながら歌え
る曲である。
姫女の余裕と遊び心から生まれた曲。
日常の家事をしながらふと思いつき、
それが終わる頃にはきっと完成してい
たに違いない。
”ピエロ”と”ラストシーン”に並ぶ。
* * * *
才能は人によっては重荷となり、
幸せの足かせとなることがある。
* * * *
決して衰えることのない
その心情の豊かさと情感の深さ
に満たされながら
姫女はいつも夢見ている
遥か彼方の地平線を
吹き抜ける風になることを
なぜならそれは感じる心を錆びつかせる
苦しみや孤独から開放させて
くれるからである
* * * *
女性のシンガーソングライターのなかには
魔女や妖精の末裔の者もいる。魔女の末裔
は美声ではないが個性的で自己演出に長け、
しかも時代の変化に敏感で計算高いので、
大衆の求める楽曲を生み出すことが出来る。
妖精の末裔は、声は子供のように幼く過剰
な自己演出を好み、時代の変化や大衆の要
請にはほとんど無頓着で、自分の個人的な
体験や欲求や感覚にもとづいた新奇性にあ
ふれた楽曲を生み出している。
だが姫女は夢の国の女王との間に
生まれた最高神の愛娘である。
* * * *
* * * *
[アルバム シューフルールから]
前アルバムにおいて姫女は自分が理想と
する自分の姿にはなかなかたどりつけない
ことを嘆いていたが、姫女が理想とする自
分の姿とはどんなものなのだろうか?
シンガーソングライターとして成功して
有名になって金持ちになるというは冗談に
もありえないのだが、たとえば何かきつい
ことを言われもすぐに落ち込まないような
人間になることか、それとも何かを議論し
ていて相手を論破するほどの知識と話術を
身に付けた人間になることか、それとも男
性の前ではいつでも可愛らしく振舞えるよ
うな女性になることか?
まあどれも違うことは確かなようだ。
〈もっと自由に〉
この曲には決して今の現状には満足しては
いけないという姫女のひたむきな決意が現れ
ている。
もう成功しているのだからこれで良いので
はないかと思うのだが。なんという健気な。
それにこの曲には姫女が理想とするほんと
うの自分の姿が 表現されているような気が
する。
〈永遠の灯〉
そしてこの曲には前作のように姫女が理想
とする真実の自分の姿が表現されている。
”遥かなる愛 歌い続けて 私は風になる”
〈愛を急がないで〉
このあまりにも穏やか過ぎる歌い出しは
まるで魔法にかけるかのように瞬時にして
聴者の心を魅了する。
姫女ときおりこのような楽曲を生み出す
のだが、それは何か特殊な発声方法による
ものでもなく、普段何気なく会話をすると
きのような、限りなく自然に近い声で歌っ
ているからである。
このような子守唄を歌う母親のようなや
さしすぎる声に人は誰でも永遠の安らぎに
いざなわれる。
この曲を聴きながら私たちは心が洗われ
るような青春ドラマを見続ける。
この愛に破局はない、
たとえあったとしても遠い未来にそのこ
とを懐かしく思い返せるようなものになる
だろう。
ところがこの曲は次のような歌詞で
ただならぬものになる
”もしも遠い未来で
今日を懐かしむとき
二人 別の宇宙
すれ違っていても”
別の星ですれ違うにはかなり長い時間を
必要とする。
でもそれが別の宇宙となると、永遠に永
遠をかけたくらいとてつもなく長い時間が
かかるのである。別の宇宙とは宇宙が作り
変えられることだ。前の宇宙と後の宇宙が
出会うことは永遠に不可能なことに違いな
いのに、何故そのような永遠の不可能性が
姫女の脳裏に浮かんだのか、奇跡なのか、
それとも最高神の娘としてのなせる業なの
だろうかれ?この穏やかな恋愛は永劫のと
きをめぐり、そして無限の空間を駆けめぐ
ることになり、その不滅性が暗示されてい
ることになるのである。私たちの日常のど
こにでもあるように青春の恋愛に普遍性と
永遠性が付与され称えられているのである。
このさりげない言葉で。
姫女はそんな大それたことは表現してい
ないというかもしれないが、真正の芸術家
というものは、ときとして、それがあたか
も何かからの働きかけのように無意識のう
ちに思いもかけない表現にたどりつくこと
があるのだ。
宇宙の本質は静寂である。こんな穏やか
な歌が永劫と無限を飛び越えて宇宙そのも
のを包み込もうとしている。
〈白い世界〉
もうたどりつけない恋愛の歌だけでは
済まされなくなっていた。
恋愛が成就したときのヴィジョンが描
かれているが、いまさら”さすらう二人”
とは、いったい姫女は何に不安を感じて
いるのだろう。
〈ポプラ〉
都会の風景に染まっていると、なぜか
破局の原因はわからない、でもそれでも
二人は別れなければならない。過ぎ行く
都会の風景になじむように。
姫女はそんな恋人たちに共感はするが、
かつてのような悲壮感はない、むしろ軽
やかだ。そして少しだけ笑みが浮かんで
いる。
〈Good-Day〉
姫女は自己の更新を目指している。
それもただ更新ではない。すべてを受け入
れ、すべてを包み込むような本来の鷹揚で
開放的な自分にもどることに。いまだ気づ
いていない最高神の愛娘としてふさわしい
ような。
〈恋の行方〉
恋愛のゴールはもうそこに見えている。
もうすべての条件は整っている。でも限
りなくそこに近づいているだけで決して
到達することはない。そして恋愛の情熱
だけがもえたぎる。
〈宇宙の片すみ〉
姫女にときおり現れる自分の弱さ。
宇宙から見たらあまりにも小さすぎる自分。
頼りげない自分。そんな自分を投げ出して
誰かに頼りたくなる。
それでも心の奥底では理想の自分を求めて
旅を続けようとするのだ。
〈新しいスタート〉
こんなに成功したのに姫女はいったい何が
不満なのだろうか。いやこれは、いつも自由
で歩き続けるには、古い自分を捨て、新しい
自分に生まれ変わらなければならないという、
姫女の自分の理想の姿を追い求め続けるから
なのだろう。だからもう”電車”のような焦燥
感も 悲壮感もない。
その朝姫女は決意を新たに胸を張って颯爽
と歩いていたに違いない。
* * * *
* * * *
[アルバム ミストラルから]
〈移ろいゆく想い〉
誰もが最初はこんな経緯をたどり恋を
失っていくのだろう。でも永遠を垣間見
せる青春の恋はなにものにも変えがたい
のだろう。姫女の自由な才気を感じさせ
る曲となっている。
〈昨日よりも、今日よりも〉
流星のように未来まで駆け抜ける愛の
喜びが歌われている。この軽やかな曲調
のため、 おそらく誰もがそれが夢だと
感じることなく、そんな夢を見るに違い
ない。
〈Heartbreak〉
青春が過ぎ去ってしまったと思うも
のは、この曲を聴いて、青春の光が強
ければ強いほどその影が濃くなってい
ることに気づくだろう。
姫女の巧みな魔術。
〈MARIAGE〉
もう手が届くところにまで迫ってき
ている恋の成就。夢想する愛の喜びは
極限に達している。
〈ミストラル〉
この曲は私にとってはずっと謎だった。
イベリア半島を吹き抜ける冷たい季節風
であるミストラルというタイトルも不思
議だったが、歌詞にも何を表現したいの
か判らないほどまとまりのなさのような
ものを感じていた。
男女の恋愛模様が取り上げられている
は確かだが、この時期に前後して作られ
たような判りやすい愛の破局劇でも夢想
する愛の成就でもなさそうだ。全体的に
は恋愛の喜びから大きくかけ離れ、現実
的な障害の前で躓き苦しむ恋愛の不安が
前面に押し出されている。
でも曲調はそのようなものとは正反対
である。最初から最後までのびやかで軽
やかである。そしてその情感は私たちが
希望をいだいたり、また何か勇気をもっ
て決意をしたときに感じるような清々し
さや凛々しさのようなものをたたえてい
る。題名がアルバムのタイトルになって
いるくらいだから、何か重要な意味がこ
の曲には込められているに違いないのだ
が。ではその歌詞を追ってみよう。
ミストラルの歌詞
灼けつく太陽が 歩道を焦がしている
さまよう二人を さえぎるように
出会いの海が今 静かにざわめいてる
あの日の想いを くすぐるように
もう一度夢を 輝いていた日々を
このまま二人 引き返したくはない
今はまだ眠ってる
未来にめぐりあいたい
涙があふれるときも
この手をはなさずにいてね
恋愛を成就させるために、私たちの周りには
どうしてこんなに多くの障害が立ちはだかって
るのだろう。
はしゃいだ毎日と 不安を繰り返して
二人はさすらう 運命の海
悲しい夜ならば 私をそばにおいて
つないだ指先 願いをこめて
すべてを受けて 駆けぬける風になる
こぼれた愛を そっと運ぶように
今はまだ眠ってる
未来にめぐりあうたび
心を閉ざさないでね
この手のぬくもりのままに
すべてを受けて 駆けぬける風になる
こぼれた愛を そっと運ぶように
今はまだ眠ってる
未来にめぐりあうたび
心を閉ざさないでね
この手のぬくもりのままに
でもその障害を乗り越えることができる
のは人間の本質だと知っている姫女は自分
たちの愛を信じて未来に立ち向かうことを
進める。
今はまだ眠ってる
未来にめぐりあいたい
涙があふれるときも
この手をはなさずにいてね
このころまでに姫女は、恋愛そして
その成就である結婚にいたるためには
様々な障害があることに気づいていた。
そしてその障害を乗り越えるためには、
決して華やかさは必要でなく、信頼と
ひたむきでひそやかな思いがあればい
いのだと思うようになっていた。
なぜなら、その”恋愛そして結婚”と
いうものを命あるものすべてが目指す
究極の姿であるというヴィジョンを姫
女は自信と確信をもって獲得していた
からである。
もちろん姫女は天なる父の最高神の
娘として、その体現者なのであるから、
そもそもは姫女自身に備わっているも
のではあるが。
そしてこの歌詞に強く表れている不
安というのは姫女自身のものというよ
りは、自分の周りの恋愛で苦しみ悩む
者たちへの姫女の強い共感のあらわれ
とみていいだろう。
そして私はこれらの疑問を解決するた
めのある結論にたどり着いた。
宇宙はその無機的物質から意識を持つ
有機的生命へと進化しつづけ、やがてそ
の意識は最終形態である男女の向かい合
う性である恋愛へと、つまり結婚へとた
どりついた。
人間意識の最高形態でもある神々を統
率する最高神の愛娘である姫女が恋愛と
結婚へのヴィジョンに満ち溢れ、あたか
もそのヴィジョンそのものであるかのよ
うに存在し続けることは至極当然なこと
である。事実姫女は今まに恋愛や結婚を
モチーフにした楽曲をあふれるように創
出してきた。
ここでいう”恋愛と結婚へのヴィジョン”
というのは生命の進化の本源的な意味や、
その最終形態となる意識の最高形態のこと
を言うのであって、決して、”女性の結婚
のあこがれというような”通俗的な意味合
いで言っているのではない。
そうするとこの曲の様々な疑問や不可
思議さが氷解する。姫女はこのころまで
にはもう”恋愛や結婚”の意味を単なる”
単なる若い女性のあこがれ”としてでは
なく、その本源的な意味としてつまり、
生命の進化の最終形態としての意識の最
高形態であることを獲得していたのであ
る。もちろんこれは天なる最高神の娘で
ある姫女にもともと備わっていたもので
あるが。いや姫女そのものがその意識の
最高形態の現われに他ならないが。
このような意識状態に達していた姫女
からして、この曲が生み出された時の姫
女自身の心情的背景をまとめるとおそら
く次のようになるだろう。
ありふれた日常風景のように、思い
がけない障害のために恋愛から結婚へ
とは簡単にはつながっていかないこと
に苦しみ悩み、未来に不安を抱いてい
る者たちを実際に目の当たりにしなが
ら、なぜそうなるのかもう十分すぎる
くらいにその原因がわかっている姫女
はそのような不安に苦しむ者たちへ共
感のいまなざしを投げかける。
そして意識の最高形態の体現者とし
ての姫女は”恋愛と結婚”に対するその
ゆるぎない信念に支えられながら、そ
れが本来人間の目指すべき究極の価値
であり希望であるのだから、たとえど
んなに不安な気持ちに押しつぶされそ
うになっても今の自分たちを信じて強
い気持ちで前に進むことを励まし続け
ている。
それがこの曲の情感の世界なのであ
ろう。
PVでスペインの草原で両腕を広げて
風を全身に受けている姫女の姿そのものが
そのことを象徴的に示している
不安をものともしない勇気や決意に支え
られた未来への限りない希望の広がりを。
ついに姫女は安易な愛の成就を飛び越え
その先の真の愛のヴィジョンを獲得した。
〈プロローグ〉
こんな姫女も珍しい。破局をこんなにも軽
やかに歌うとは。時代の若い女性たちの感性
に対応したのだろうか。
〈告白〉
この曲を聴いてどれほどの若い女性たち
が告白の勇気を得たことか。
〈さかまく未来〉
姫女の曲作りはきっとこんなふうにして
はじまるのだろう。
何気ないありふれた日常の風景を目にし
ているとふと情感があふれるように沸き起
こり、それが曲想となって頭に浮かぶと、
それを何日かかけて熟成させながらやがて
歌として醸成させていくのだろう。
この曲には今自分が恋愛をしているこ
とを、誰かに知ってもらいたいような希望
と喜びに満ち溢れている。
〈ミッドナイト・ブルー〉
ときおり理由もなく姫女は落ち込む。でも
心を開放している限り、この世界この宇宙で
起こるあらゆることが洪水のように姫女の心
の内奥にまで押し寄せてきているのだから、
それは仕方がないことだ。
それにもかかわらず姫女はいつでも希望の
光を見出そうとしている。何とひたむきで健
気なことか。
* * * *
傑出した能力は人によっては重荷となり、
幸せの足かせとなることがある。
だが姫女は違うようだ。自分の才能に真
正面から向き合いあたかもそれが運命であ
るかのように抱きとめている。
そしてそれらの才能は、成功し称賛を
受けるとさび付くが、姫女の場合決して
その輝きは衰えることはない。それは世
界を映し出す心の内奥から自然と沸き起
こる情感を創作の源泉としているからで
ある。
* * * *
[アルバム満天の星から]
〈無敵のキャリアガール〉
最初のメロディーが頭に浮かんだ瞬間、
あとの残りは最後まで流れるように続い
たに違いない。”ピエロ””ラストシーン”と
同じように、姫女の視線は珍しく自分の外
部に向けられ、恋を遊ぶように楽しむよう
に作られている。
当時流行っていたトレンディドラマのエ
ンディング曲になっていてもおかしくない
ような楽曲。もし姫女がこのような曲を数
多く作っていたら、きっと音楽界で重要な
位置を占めるようになっていただろう。
〈夢見る頃を過ぎても〉
いつしか自分は青春に距離をとりつつある
ことに姫女は少し戸惑いをみせながらも、そ
れを前向きに捉えようとしている。
最初の出だしがそれへと私たちを導く時間
の流れのやさしさを感じさせる。
〈フォーエバーロマンス〉
男女の出会いとはそもそも宇宙規模の奇跡
的なことであると、はるか銀河を渡ってきた
姫女は力説する。
〈満天の星〉
姫女は成功した。それによって多くの人々
が姫女を取り巻くようになった。そのことは
いやがうえにも姫女の行動や考えを制約し縛
ることになる。
そのことが姫女が理想とする自分の姿から
自分をだんだん遠ざけてしまうことに気づき
始めた。姫女は不安になりそっと星空に助け
を求める。もし父なる最高神がそれを聞きつ
ければ直ちに連れ戻そうとするのだろうが。
〈夏のスピード〉
成熟しつつある姫女でも恋を夢想する、
それも少女のような感覚の恋を。
この初老の私でも若くて美しい女性を目の
前にすると見苦しいくらいうろたえる。少年
のように。
〈ピリオド〉
姫女はときおり悲哀に包まれる。
悲哀を宇宙の重みを支えているから姫女はそ
れを受け入れる。そしてお互いにその理由も
わからず別れなければならなくなった男女の
悲恋も。この曲は物語のように姫女の悲哀に
支えられる。
〈星空はいつも〉
もしかしたら姫女は最高神に見守られて
いることに気づいているのだろうか。
〈卒業〉
きつい言葉だから傷つくとは限らない、
やさしい言葉だから傷つかないとき限らない、
相手から思いがけない言葉を聞くと傷つく。
この曲も物語のように姫女の悲哀に支えら
れる。
〈笑顔にはかなわない〉
笑顔には魅力がある。
とくに赤ちゃんの笑顔は人間の輝かしい
勝利を表している。
そんな笑顔を持つ理想的な男性との永遠
の愛を、この曲を聴く若い女性たちに夢想させる。
* * * *
これまで筆者は、姫女のその自分の心に
誠実に向き合う鷹揚で開放的な性格からし
て、それまで自分の心にため込まれている、
すべての楽しいことや辛いことの思い出、
そしてずっと心に残り続けるこだわりやわ
だかまりに寄り添うように見つめなおして
は、それらをありのままに正直に歌として
表現することによって、心がより自由に開
放的になっていると思っていた。
だが実際は違っていたようだ。心の片隅
にはどうしても折り合いがつかず、わずか
だか黒い思い出の塊が残っていたようだ。
そしてそれが何気ない日常の風景や出来
事がきっかけとなって、寂しく悲しい気分
におちいると、そんな過去の辛く暗い思い
出と結びつき、もう閉じこもってしまいた
いくらいの激しい気分の落ち込みや苦痛に
おそわれるようだ。
さらに付け加えると私は今まで姫女を誤解
してきたようだ。というのも、姫女が、楽し
い思い出だけではなく、自分の心を暗く閉鎖
的にしている要因でもあるそれまでのさまざ
まな苦しく辛い思いでや出来事を、歌に託す
ことによって、それらの苦しみや辛さから解
放されて、本来のおおらかで解放的な性格を
取り戻しているに違いないと。
ところが少し違っていたようだ。
姫女は自分の理想像を求めて努力し成長す
る人だった。
努力し成長するということは、立ちはだか
る困難や苦境を乗り越えようと悩み苦しむこ
とだ。
私の好きな小説家や詩人や画家はすべて死
ぬまで悩み苦しみながら成長を続けた人たち
である。まさに真正の芸術家たちである。
それならば姫女は真正のシンガーソングライ
ターということになるが。
姫女は”感じる”ということを大切にしている。
それはアルバムミストラルのPVに草原で両手
を広げ全身で風を受けているシーンに象徴的に現
れている。さらにこれにはもうひとつのことが象
徴されている。それは姫女はおおらかで開放的な
性格であるということが。
普通おおらかで開放的な性格といったら、あま
り物事にこだわらない大雑把なという、むしろ”
感じる”ということとは対極にあるように見える
が、その両者を兼ね備えている姫女はそれらを両
立させ、そこを汲めども尽きない創作の源泉とし
ている。
ところが開放的な性格のまま感じる気持ちを
持ち続けるということには危険が伴う。という
のもこの宇宙で起こるあらゆる出来事を受け入
れながら、それらにいちいち対処するというこ
とは並外れた意志力分析力洞察力が必要とされ
るからである。なぜならこの宇宙で起こるあら
ゆる出来事とは、たくさんのよいこと楽しいこ
とだけではなく、あらやる悲しいことや悪いこ
とが、そして天使や妖精や悪魔や鬼や天邪鬼と
呼ばれるものも含まれるからである。
ほとんどの人は自分が好きなもの興味がある
ことには目を向けるが、不快なことや興味のな
いものには知らん振りをして忘れるようにして
いる。なぜならそうしないと精神に破綻をきた
すからである。ところが姫女はそれらに全身全
霊で対処してきた。そしてくたくたになりなが
らも、そこから多くの楽曲を生み出してきた。
姫女は見た目以上にに怜悧で気丈であるよう
だ。ちなみに姫女の歌には天使や妖精の姿が見
えるが、 悪魔や鬼や天邪鬼の影は少しも見え
ない。推測に過ぎないが彼らは姫女の真の正体
を知っていて姫女に近づくことを恐れたようだ。
* * * *
[アルバム SWEET HEARTSから]
〈山あり谷あり〉
気がついたらいつの間にか大人の女性になって
いたという感じで、だいぶ同世代の女性たちの現
実的な生き方に影響を受けているようです。
〈Dear Friend〉
天性の作曲能力は衰えることはない。
〈海岸通り〉
姫女の恋愛感に変化を感じるのは気のせい
だろうか。
〈あなたの隣〉
こんなにも軽やかに、こんなにも余裕のある
恋が大人の女性の恋と言いたいのでしょうか。
〈明日への道〉
姫女は相変わらず苦しみと絶望の谷から喜び
と希望に輝く山の頂を見続けている。
〈ラビリンス>
姫女は人生にも迷うが恋にも迷う。それでも
誠実にひたむきに努力していたらいつかは必ず
喜びと希望に光り輝く山の頂にたどりつけるこ
とを信じている。
〈夢の途中〉
姫女のこの地上で人間として生きることへ
のあふれんばかりの自信。幸せへのゆるぎな
いヴィジョン。いますぐにでもつかめそうな
幸せへのヴィジョン。
〈Naturally〉
今まで色んなことを乗り越えて生きたのだ
から、これからの未来もきっと乗り越えられ
るはずだと確信する。
ようやく言葉に出して言えるようになった
自信と決意、そして自分に対するゆるぎない
信頼、駆け抜ける風になることをいつも夢見
ていた青春を遠くに望みながら。
〈ハレルヤ〉
ついに姫女は自分の将来をたくせるに値す
る未来へのヴィジョンを獲得した。あとはただ
ひたすらその輝かしい未来に向かって歩き出す
だけだと決意する。
* * * *
* * * *
このころ父なる最高神は、次の二つの曲
”明日への道”と”ラビリンス”を耳にして、
何を勘違いしたのか、姫女がいまだに地上
で悩み苦しんでいると思い、姫女をを天上
に連れ戻す決意をした。そしてそれを姫女
に寄り添っている女神ムーサに命じた。
ある夜女神ムーサは、姫女がリビングで
ソファーに座ってくつろいでいるとき、初
めて姫女の前にその姿を現した。
そして自分はあなたをずっと見守ってい
たこと、そしてあなたは天上を支配する最高
神と夢の国の女王との間に出来た子供である
ことを告げた。
そして戸惑う姫女を前に女神ムーサは言葉
を続けた。
「今父なる最高神はあなたのことをとても
心配しております。いまだに悩み苦しんで
いるからです。そこで最高神は私に命ぜら
れたのです。あなたを連れ戻すようにと。
どうですか、私といっしょに帰りましょう。
永遠に生きられる夢の国に、そこではあな
たはあなたが望む若さと容姿のまま永遠に
生きられるのです。さあ、帰りましょう」
だが姫女はやさしく笑みを浮かべながら
顔を横に振って言った。
「私ははここに残ります。なぜなら、
今まで私を支えてくれた
沢山のファンやスタッフの皆さんから
離れることは出来ませんから。
私はこの地球で、人間として、
他の人たちといっしょに喜びや
悲しみや苦しみを分かち合いながら限り
ある人生を送ろうと思っています」
ムーサが気迫をこめて言う。
「そこでは永遠に生きられるのですよ」
だが姫女は再び断った。
女神ムーサはその後何度も誘ったが姫女
はそのたびにやさしく断った。
ついに女神ムーサは諦めた。
そして姫女にしばらくのあいだ眼を閉じて
いるようにと言って、その場を離れた。
やや不安そうに顔を曇らせながら、
でも最後には、これからの姫女の人生を
祝福するかのようにやさしく微笑みなが
その姿を消した。
しばらくして姫女は眼を開けた。
そして
「あら、今何が起こったかしら」
と言いながら不思議そうな表情をした。
それはこの出来事のいっさいが女神
ムーサによって姫女の記憶から消され
ていたからである。
* * * *
なぜ姫女は永遠の命を捨て有限の命を生
きることを選択したのだろうか?
もし夢の国に帰ればその絶頂期の美貌と
才能のまま永遠の青春を生きられたという
のに。
姫女はもう青春は歌いきったと思った
のだろうか?
ちょうどこのころ姫女は楽曲《夢の途中》
を完成させていた。
その歌詞
見つめあうって 幸せなことね
あなたの声がききたくなる
ふと目ざめたなら
恋をしている 素敵な瞬間
すべてのものがきらめいてる
優しさがあふれ出す
なにげなく過ぎゆく日々を
二人分け合って
永遠の時を 越えて行こう
ときめきと 揺れる想いを
胸に抱きしめて
ゆるがない愛に いつか届くように
夢の途中 迷った時にも
心のままに歩いていて 自分を信じて
どんな答えも まちがいじゃないと
誰もがいつか気付くでしょう
とまどいをくり返し
ほら いつもあなたのことを
そっと守りたい
やわらかにそよぐ 風のように
輝きと光るハードル
すべてとびこえて
ゆるがない明日に 続いていきたい
巡り 巡る 季節の中で二人が
出逢った偶然 運命にぬりかえて
ほら いつもあなたのことを
そっと守りたい
やわらかにそよぐ 風になって
ときめきと 揺れる想いを
胸に抱きしめて
ゆるがない愛に いつか届くように
ほら もっとあなたのことを
強く守りたい
ゆるがない愛に いつか届くように
ここに描かれているのは紛れもなく、
姫女のこの地上で人間として生きる
ことへのあふれんばかりの自信である。
幸せへのゆるぎないヴィジョン、そして
いますぐにでもつかめそうな幸せへの
ヴィジョンに満ち溢れている
知らず知らずのうちに、
苦しかった青春の悲哀も不安も乗り越え、
ようやく幸せをつかめそうな穏かな
気持ちに支えられた毎日を過ごしながら
この楽曲にこめられている
周囲をも包みこむかのような
幸福感が醸成されていたのだろう。
そして”Naturally”と”ハレルヤ”が
姫女の決断の後押しをしたのだろう。
* * * *
姫女の決意を知って報告を聞いて父なる
最高神は嘆いたが、愛娘が決めたことなので、
最後は姫女の地上での幸せを願いながら諦め
るしかなかった。
* * * *
* * * *
そして私(筆者)も、もうこれで充分ではない
かと思い姫女からは離れていった。
* * * *
いつしか私はあたかも封印したかのように
姫女の音楽をまったく聴かなくなっていた。
ほんの数年間ではあったが、壮年期の私が
姫女の歌を聴き続けたのは、姫女の作り出す
情感の世界にそれまでの苦難な青春期に感じ
た様々な思いを重ね合わせるかのように共感
することによって、癒され慰められ、そして
自分の存在が有意義なものと感じられからに
違いないあろう。
というのも共感することによって”音”が本
質的に備えているその共同体意識を獲得する
ことによって、それまでの疎外感や孤独感が
和らげられたからであるに違いない。
なぜ私は姫女の歌によって癒され慰められ、
そしてそれまでの孤独感や疎外感がやわらげ
られたのだろうか。
私たちを取り囲む社会の根本をなしている
のは物理的世界としての自然である。その自
然は人知では計り知ることのできない、しか
も冷徹と思えるほどの合理性に支配されてい
る。そのうえ自然は日々変化し更新し続ける
ことによって、私たちの精神をあざ笑うかの
ように翻弄し続ける。そのために人間は悩み
苦しみ、そして躓き挫折する。そのことは
”運がいいとか悪いとか”、また、”努力が必ず
しも報われるものではない”という形で、私た
ちの意識に表出される。
やがて自然は最終的には人間の肉体と同時
にその精神をも解体して漆黒の闇と絶対零度
の原子にかえす。
この冷徹な合理性に支配された現実の前に
果たして私たちはどれほど耐えられるだろう
か。死に物狂いで私たちはこの現実と折り合
いをつけようとする。そんなとき姫女の作り
出す情感の世界は、なんと穏やかで心地よい
のだろうか、そこには永遠の青春がある、愛
の真実や奇跡がある、そして時間を止めるほ
どの幸福感につつまれながら、常日頃眼に見
えるものだけに支配され蹂躙されていると感
じている私たちは癒され慰められる。
だが人間の真理はいつもその反対側に横た
わっている。
そのとき私は四十を過ぎていた。
もう時間はなかった。
それまでとは違う未来の新しい自分を
獲得するために、変化し更新する世界に
立ち向かいながら、自分も変化し更新し
ていかなければならなかった。
そして私は旅立つように姫女から離れた。
もちろん諦めることのない夢を抱きながら。
* * * *
その後私は何度か姫女のついての出来事を
テレビから噂話のように聞くことがあった。
いずれにせよ地上の生活に懸命に順応しよう
としていることがわかったが、どのような形
であれこのまま平穏に続くことだけを願った。
そしてときおり、ほとんどマスメディアに
取り上げられなくなった姫女について話す者
たちがいた。その者たちは姫女ついてはなす
とき、みな自分の過去の大切な思い出を語る
ように懐かしそうに話すのだった。
そんなとき私はいつも聞かないふりをして
いた。
* * * *
* * * *
あれから四半世紀、
私は再び姫女の音楽を聞き始めた。
何にも変っていなかった。
その楽曲の持つ心情の豊かさや情感の深さに
私は再び心の底から感動し魅了されていた。
そして私は姫女について
何かを書き残したいと思った。
現在姫女についてのあらゆる情報は
インターネットで得ることができる。
今も活動していることが何となく知る
ことができる。なんとなくである。
なぜなら私はどうしても現在の姫女に
ついてそれほど詳しく知ろうという気
持ちにはなれないからだ。
それによると姫女は現在人間として
この地上での自分の幸せだけではなく
他の人たちの幸せをもひたすら願って
いることがわかった。
かつて自分の心の内奥を見つめなが
ら数々の楽曲を生み出していたことは
紛れもなくこの地上に住む人間として
成長を続けながら、自分が理想とする
人間性の獲得とその完成を目指してい
ることに他ならなかった。
そして姫女そのことを見事に成し遂
げたようである。だから私はそのこと
に何の異を唱えるものではない。
でもこの世界から捨てられたような
喪失感の置き場所が見つからない。
私がかつてこのことに薄々気づいて
いたからだろうか?
完全に閉じられてしまってたかのよ
うな神性の扉。どうすれば再びその扉を
開くことが出来るのだろうか?
現在人間として家族とともに幸せに暮
らしている姫女に 求めると云うのか?
姫女の歌は今でもファンたちに希望と勇
気を与えている。
でもそれだけではない、姫女自身もた
くさんのファンたちに支えられているの
だ。もし姫女がファンたちの支えを失っ
たら、姫女はこの世から朝露のごとく消
えてしまうだろう。なぜなら天上の神々
は人間の支持を失ったら、消滅してしま
う運命にあるのだから。
メイプルシロップを得る
ために人はその幹に
深く穴を開けるという
漆を得るために人は
その幹に何本もの無残
な傷をつけると云う
砂漠で水を得るためには人は
そこから容赦なく砂を掻き出し深く深く
掘り下げなければならないと云う
桜は春に美しい花を咲かせる
ためには冬のある期間その寒さ
にさらされなければならないという
NO RAIN NO RAINBOW
姫女は全身全霊でもってこれを成し遂げ
てきた。そして神の子姫女は多くのファン
の支えを必要とする人の子となった。だか
らもうこれで充分なはずだ、これ以上姫女
に何を求めようとするのか。
* * * *
ときとして時代は、祝祭のような
熱狂と惑乱でもって人々を巻き込み
選ばれた者たちの才能を浪費させながら
時間を止め自らを永遠ならしめようとする。
そしてその触手は姫女にも伸ばされていた
ようだ。
果たして時代は姫女をも取り込むことに
成功したのだろうか?
* * * *
<ヒロイン>
これは私が姫女の曲を聴かなくなってから、
ふと耳にした曲である。たしか1994広島
年アジア大会のNHKのイメージソングであ
る。おそらく依頼によって作られたものにち
がいない。というのもこの曲の至る所に作意
が感じられ、それまでの様々な楽曲の印象的
なモチーフが連想されたからである。
だから当時私は、物に触れて自然と心の奥底
から沸き起こるものだけではなく、どんな依頼
でも、その要望に合わせて作曲ができるという、
決して衰えることのない姫女の才能の包容性や
余裕さをその当時は感じたものだった。
そして今再び姫女の曲を聴くようになった今、
私は改めてこの歌詞にふれて愕然とした。とい
うのも私が姫女から離れてこの四半世紀、私が
これまでどんな思いで生きてきたかを、まるで
その後の私を予言していたかのように、歌詞と
して歌われていたことを知ったからである。
その歌詞
・・・・・・・
・・・・・・・
大切にしてた夢 いつかは
失くしてしまうのかな
何度もつまずくたび しぼんだ
気持ちをにぎりしめて
言葉にできない熱い情熱を
胸の奥で確かめてる
かなわないことと あきらめるよりも
わずかな奇跡を 信じ続けたい
答えのない世界で 誰もが
孤独と戦ってる
けれどもその瞬間 輝く
・・・・・・・
明日が見えずにうつ向いていても
拳の中理想抱いて
無駄なことなんて何ひとつないと
優しく背中を押してくれるから
かなわない夢と あきらめるよりも
わずかな奇跡を 信じ続けたい
・・・・・・・
・・・・・・・
アジア大会のイメージソングで曲名が
”ヒロイン”なのだからきっと大会のメダ
リストをたたえる内容なのかなと思いが
ちだが実際は全く違う。
私たち普通の人間として生きていくた
めに、どうしても乗り越え克服していか
なければならないこと、それも誰もが経
験するような、日常のありふれたこと、
そんな些細なことを、どんなに躓いても
勇気をもって乗り越えた者たちを、姫女
は”ヒロイン”として称賛するのである。
これは姫女の心情の豊かさや情感の深
をいっぱいに湛えたその優しい眼差しが
この世界の片隅のどんな小さなことにも、
どんな些細なことにも変わることなく向
けられているということなのだ。
(歌詞)
何度もつまずくたび
私は齢を重ねれば分別をわきまえより
理性的な行動ができるようになると思っ
ていたが、 実際はそうはならなかった。
見苦しいほどの失敗や過ちは若い時とそ
れほど変わらなかった。でも決して自分
の目指していることを見失うことはなか
ったのだが。
(歌詞)
言葉にできない熱い情熱を
胸の奥で確かめてる
どんなに周囲から不信の眼差しを向け
られようとも、やはり自分にはこれしか
ないんだと 言い聞かせるしかなかった。
(歌詞)
かなわないことと あきらめるよりも
わずかな奇跡を 信じ続けたい
でも、もちろんそれは決して大それたも
のではなかった。
(歌詞)
答えのない世界で
誰もが孤独と戦ってる
どんな些細なことでも何かを成し遂げよう
とした場合、やはり最後は自分自身が頼りな
のだ。
(歌詞)
無駄なことなんて何ひとつないと
優しく背中を押してくれるから
そうはいっても心の奥底にはときおり誰か
に頼りたいという気持ちが芽生えることも確
かなのだが。でもやはり最後は自分だ、自分
信じて前に進むしかない。
(歌詞)
かなわない夢と あきらめるよりも
わずかな奇跡を 信じ続けたい
* * * *
* * * *
私は今再び姫女と出会っている。
現在は姫女の情報はネットとYoutubeで
得ることが出来る。
私は今人生の四コーナーを周り目の前には
そのゴールラインがちらついている。
それらなのなぜ私はいまだに姫女の楽曲に
魅了されるのか?
その呼び起こす感動は当時と何も
変わっていない、
それは最初に出会った二十五年前から
私は何も変わることなく、いまだに
青春の迷路をさまよい続けていると
いうことなのか?
それとも姫女の心情は普遍的なのか?
* * * *
あの夜、ムーサが姫女のもとを離れた
とき、姫女は、私たち人間の社会に残り、
私たちと同じ人間として、哀楽をともに
しながら進化する心の体現者として生き
ることを決断したのだったが、苦難と愛
憎に満ちたこの現実社会を人間のように
たくましく、そしてしたたかに生き延び
る能力を決して充分に備えていた訳では
なかった。
* * * *
なぜ私は姫女について語りつくすことが
出来ないのだろうか?
私はこの小論で姫女を語るために何万と
いう語を費やしてきたが、少しも何かをな
しえたという充実した気持ちにはなれない。
何万の言葉で表現される観念も、決して
姫女のわずか数小節にも及ばない。
* * * *
姫女の才能は蓄えられた湖の水のような
才能ではないということだ。
周囲の環境の支えられて滾々と湧き出る
泉のような才能なのである。
だからもし周囲の環境が悪化(ファンの支
えを失うこと)してしまえばたちまちにして
泉は枯渇してしまうだろう。それほどまで
に姫女は繊細でもろいのである。
* * * *
失われたもの
姫女の永遠の青春とその神性
* * * *
私たちは姫女の生き方から次のことを学ぶ。
今まで私たちがずっと思っていたところの
理想的な人間像というのは決して有徳の人と
いうようなものではないということを、それ
は思い違いであり、本当に私たちが目指すべ
き理想的な人間というのは、自分の存在がい
つも誰か他の人をに支えることができていて、
また自分の存在がいつも誰かほかの人に支え
られているような、そんな人間がであるとい
うことだ。
* * * *
最後に姫女苑の花言葉
ひたむきと素朴さ
* * * *
十日ほど前の朝、山小屋のような
我が家の玄関を開けると、向かいの土手に
咲いている白い一輪の花が
目に入ってきた。
まるで挨拶するかのように
次の朝も、
そして次の朝も、
やがてその花はあっちこっちに咲くようになった。
そして今、我が家の周りには、
ヒメジョオンが咲き乱れている。
* * * *
* * * *
補記
私はこの小論を書くにあたって”天才”とか
“名曲”とかという言葉を絶対に使わないよう
にと決めていた。それは成功したような気が
する。でもそのためか自分でも理解できない
くらい文章が晦渋なものになってしまった。
これはひとえに私自身の力量不足によるもの
である。
それで直感的な表現になってしまった”生命
の最終形態”とか”意識の最高形態”については
本来なら生命を賭した大著をもって論述される
べき代物なのだが、今の私にはその能力も余裕
もない。
汲めども尽きない姫女の才能に触発されたか
のように私自身にも姫女について語りたいこと
が次から次へと沸き起こってくる。でもきりが
ない、というより意味がない。なぜなら姫女の
楽曲からもたらされる感動に比べたら、どれほ
どの言葉をもって書かれてもそれは無に等しい
からである。
さらに付記
現在も姫女はその純粋性に突き動かされながら
感じるままに曲を作り歌い続けている。
そこにはますますきめ細やかさが増してきてい
る心情の豊かさや情感の深さが反映されている。
十代から途切れることなく歌われ続けている恋
愛情趣も純化された恋愛ドラマのように決して色
あせることはない。
これで恋愛は決して若者の特権ではないことに
気付かされる。
なぜなのか?
ついに姫女の本質に迫る時が来たようだ。
源氏物語に挿入されている多くの短歌の作者
と同じように、現実的な色情に特別に興味を持
っているからではなく、恋愛というものを生き
物の最終形態としての人間の意識の最高形態、
つまり最高の価値として、しかもそれを人間の
最も重要な本質として、姫女も洞察しているか
らである。
言い換えるとそれは、源氏物語の作者にも姫
女にも、恋愛のヴィジョンが生き物の最終形態
である人間が目指すべき意識の最終形態にして
最高の価値となるイディアとして直観され獲得
されているに他ならない。
* * * *
* * * *
最後の試練を乗り越えら
れんことをここに祈る。
* * * *
悲しいほどひたむきに
* * * *
* * * *